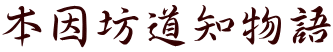
~生涯、真の実力を出せなかった棋士~ 作・妖怪百目
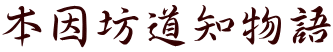
~生涯、真の実力を出せなかった棋士~ 作・妖怪百目
五世本因坊道知は、先代の大名人本因坊道策が有望な後継者を次々と20代での早逝で失うことで、最後に本因坊家を託された。
道知は、道策が才能を見込んだ天才であったが、時代は囲碁界の停滞期であり、碁打衆同士が地位の安泰を求めて馴れ合いの対局が繰り返されていたため、その実力を発揮する場がなかった。
道知は、棋力では他の碁打衆より頭一つ二つは抜けていたが、他家元の立場を慮って手加減をした対局を繰り返すことになり、碁打衆同士の約束では、実力では第一である道知については、しかるべき時に名人碁所に推薦することになっていた。
しかし、いつまでもその約束を果たそうともしない碁打衆に業を煮やした道知は『約束を果たす気がないのなら、これからは本気で打つことにする』と宣言して他家を震え上がらせるのであった。
1.《 序 》
2.《 1.幼年道知・元禄3年(1690)~元禄11年(1698) 》
3.《 2.道知、本因坊に入門す・元禄13年(1700) 》
4.《 3.道策の遺言、道知五世本因坊となる・元禄15年(1702) 》
5.《 4.小倉道喜との出会い・元禄15年(1702) 》
6.《 5.道節(井上因碩)本因坊に住む・元禄15年(1702) 》
7.《 6.道知、御城碁に出仕す・元禄15年(1702)》
8.《 7.安井家の言いがかり・元禄16年(1703)~宝永2年(1705)》
9.《 8.道知、仙角の争碁・宝永2年(1705)~宝永3年(1706) 》
10.《 9.道節、道知の後見を解き、道知、道節を名人に推す・宝永3年(1706)~宝永4年(1707) 》
11.《 10.道節の名人襲位と、安井、林の交換条件・宝永4年(1707) 》
12.《 11.琉球棋士里之子の来日との対局・宝永4年(1707)~宝永7年(1710) 》
13.《 12.道節、碁所に就く・宝永7年(1710)~宝永8年(1711) 》
14.《 13.道節の発陽論・宝永8年(1711)~正徳3年(1713) 》
15.《 14. 道知、御城碁の手加減・正徳3年(1713)~享保4年(1719) 》
16.《 15.道節亡き後、約束の履行を迫る道知・享保4年(1719) 》
17.《 16.本気で打つ、と脅す道知・享保4年(1719) 》
18.《 17.道知、名人碁所になる・享保4年(1719) 》
19.《 18.道知の晩年・享保4年(1719)~享保12年(1727) 》
20.《 19.道知、没す。その後・享保12年(1727)~ 》
(登場人物)
本因坊道知
第五世本因坊。名人碁所。わずか13歳で名門本因坊家を継いだ天才棋士。しかし同世代のライバルに恵まれず、修業時代を除けば本気で力を出して碁を打つことのなかった不遇の棋士
本因坊道策
第四世本因坊。囲碁史上最強ともいわれる大名人・碁所。高弟の早逝などにより跡継ぎに恵まれず、晩年に道知の天才を見出し本因坊家を継がせる。一説には道知は道策の実子との説もある。
三世井上因碩・桑原道節
元は本因坊道策の弟子。本因坊家を出て井上家を継いだが、道策の要請により道知の養育に心血を注ぐ。
※著者注:井上家は代々が因碩を名乗るため、跡目時代の名か隠居後の名で区別される
※著者注:井上家世系は、後に幻庵の時代に中村道碩を開祖として一世ずつ繰り下げられているため、この当時で言えば、桑原道節は三世因碩が正しい。
安井仙角
碁打衆、安井家四世。主に道知と同時代で安井と呼ぶときは、この仙角のこと
林門入
碁打衆、林家当主。林家は、代々が門入を名乗るので、跡目時代の名か隠居後の名で区別される。
※道知と同時代では、玄悦、朴入、因長が就いている。
小倉道喜・秋山仙朴
本因坊家弟子の異端児。晩年、棋書出版をめぐり本因坊家と事件をおこす。
屋良里之子
琉球文化交流使節の一員。琉球第一の棋士。
(用語)
・碁所(ごどころ):江戸時代の碁打衆(碁方ともいう)を統括する最上位の役職、地位。
・御城碁(おしろご):年に1度、江戸城御黒書院にて、将軍御上覧にて碁を披露する催事。碁打衆にとっては、これに出場することが最高の栄誉となる。
・当時の段位と手合割について
手合割は、一段差を半子として、互先・先互先・定先・先二・二子・二三、と進む。
九段=名人
八段=半名人(江戸後期には準名人と言い換えられる)
七段=上手(じょうず)、通常の最高段位
六段=上位並(じょうずなみ)