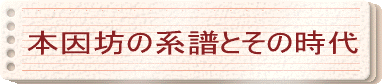 続編 本因坊名跡争奪全日本囲碁選手権戦の時代
続編 本因坊名跡争奪全日本囲碁選手権戦の時代1.序章 2.利仙・昭宇・薫和 3.昭宇と関西棋院 4.坂田の苦汁
5.秀格9連覇(前半) 6.秀格9連覇(後半) 7.栄寿独占の時代
8.林海峰から木谷一門へ 9.コンピュータ・宇宙流・殺し屋
序 秀哉から東京日日・大阪毎日新聞を経て、本因坊の名跡は日本棋院に譲渡されます。日本棋院は本因坊の名跡を実力第一位のものが勝ち取るという選手権戦を開催することになりました。
しかし、初めての大掛かりな大会であり、全棋士の公平な参加という点について、規定整備の段階から多くの問題が発生しました。
まず、予選、本戦はトーナメント形式とし、公平のためにコミ碁を採用することを決めましたが、コミの採用に長老棋士からクレームがつきます。
現代なら当たり前のコミも、古くから修行してきたものにとっては「黒番は堅実に勝ち、白番は変化を求め作戦を練る」と白黒両方の打ち方を学ぶものであって、盤外の目数を勝負に持ち込むのはおかしいと言う意見もありました。
新聞社は、本因坊戦の数年前に開催したトーナメント大会で、段割りによってコミなしの手合が行われたことを例にとって説得します。いかに長老・高段の棋士といえども、実力が段位を上回る伸び盛りの若手棋士の先や二子の手合をこなせません。
そのトーナメントは2度とも低段棋士が優勝する結果となり、そういうこともあって、次に行われる選手権戦では実力第一位を決めるものであるから、対等な立場あるべきと説得し、また、低段予選を勝ち抜いて上位の段の予選に参加する方式をとることで、総互先とすることは納得させました。
しかし、それでもなお、コミ碁は邪道であるとして反対する長老・高段の棋士もいました。全員の賛意を得て選手権を開催したい新聞社は、反対する棋士の要望を聞き入れて、「トーナメントは先番の利を公平にすべくコミ碁とするが、上位2名の決勝戦はコミナシ六番碁とすること。また、コミ碁の不合理性について私見を述べるので新聞掲載すること」で決着しました。
低段予選の勝ち抜き者4名と、七段4名を加えた8名で本戦を戦いますが、これがまた変則的なルールでした。
8名が4度のトーナメントを行い、各回毎に優勝者6点、2位5点、3位4点、4位3点、1回戦敗者1点として、合計点数の上位2名により決勝六番碁を行うというものです。
これは、当時最も人気のあった木谷實、呉清源の優勝争いになるに違いないと読んだ主催者が、2人の目玉対局が何局も見られるようにと考えたといわれています。
しかし、主催者の思惑ははずれ、呉清源は2度優勝したものの、あとの2回は1回戦負けの14点で3位、木谷は1度優勝したが、3度の1回戦負けで9点。
決勝に進んだのは、優勝2位3位1回戦負け各1回16点1位の関山利一と、優勝はないが1回戦負けもなく15点2位の加藤信となりました。加藤はコミ碁の不合理を説いた当人でした。
利仙・昭宇・薫和 第1期本因坊戦の決勝は関山、加藤によって、約束通りのコミナシ六番碁で行われます。
木谷と呉の戦いのような華やかさはないものの、関山は大手合優勝7回(呉の6回を上回る)、加藤は大手合制度で初の七段昇段者と、その実力は本因坊を争うに十分でした。
勝負は互いに黒番勝ちの3勝3敗となり、規定によってトーナメント勝ち点1位の関山利一が優勝、第1期本因坊利仙の雅号が送られることになりました。
本因坊の号は、第3期以降は本人が好みでつけられるようになります。
第2期は、9人の七段と、実績推薦、予選勝ち抜き2名で最終予選を行い、本戦リーグに加藤信、木谷実、橋本宇太郎、篠原正美の4名。橋本が全勝で優勝して挑戦者となりました。
挑戦手合は、昭和18年。すでに第二次世界大戦の最中であり、5番勝負に短縮し、同時に4目半のコミ出しに変更されていました。
しかし、このとき利仙はすでに精神性の疾患が相当に重く、第1局を簡単に失ってしまいます。
続く第2局の対局中途で利仙は盤上に倒れ、勝負は一時棋院の預かりとなります。
病気回復を待つ、あるいは一番弟子の梶原武雄に代打ちさせるなどの案がありましたが(実際、梶原と橋本を打たせて、梶原が勝ったときは師の利仙の病気回復まで預かりとする案が採用されそうになりました)、結局は利仙の棄権負けとして、第2期本因坊昭宇が誕生しました。
続く第3期、昭和19年〜20年は太平洋戦争末期の混乱の中で、棋戦の存続や棋譜掲載の目処もないまま予選が行われました。
毎回対局方式が定まらない混乱のなか、第3期は、五、六、七段予選を勝ち抜いた5名と、八段の瀬越憲作、加藤信、木谷実、呉清源の計9名が、変則リーグで4局を打ち、上位3名の決勝リーグを勝ち抜いた岩本薫が挑戦者となります。
しかし、東京は空襲が激しくなり、日本棋院も消失。先に郷里に疎開していた瀬越の世話で、広島で挑戦手合が打たれることになりました。
この期の挑戦手合は、第1期と同様にコミナシの六番勝負でした。
しかし、広島での世話人が、広島市内での対局は危険として対局に協力してくれません。留守の間に第1局を打ったところ、世話人に激怒され、対局場を追い出されるハメになります。
そこで第二局は、少しでも落ち着いた場所に、というわけで、8月4、5、6日、広島市の中心部から10Kmほど離れた五日市に場所を移して対局することになりました。この10Kmの移動が命を救うことになります。打ちかけ3日目の朝、空襲警報解除を待って、打ち掛けの手順を並べ直して対局を再開しようとしたとき、窓ガラスを破り、碁石を吹き飛ばすほどの風が起きます。外を見ると広島市街地方面が燃えている様子で、何か大規模な爆発でもあったようだと思いながらも、とにかく周りを片付けて碁を打ち終えます。
対局が終わって帰路に着こうとしたところ、初めて市街から逃げ延びる大勢の人を見て、どうやらこれはかなり大規模な攻撃を受け、偶然にも自分たちは碁を打つなら場所を移せという命令に従って命拾いしたことがわかりました。
さすがに第3局以降をこのまま続けることができず、一旦は中止。原爆の日も、その後の戦後混乱期も、希望はなくとも棋士は碁を打つことが使命と、11月から千葉県と東京に場を移して継続し、3-3の打ち分け。翌年改めてコミ出し3番勝負を行い、岩本が第3期本因坊薫和となりました。
昭宇と関西棋院 第4期は、本因坊戦設立当初から本命と見られていた木谷實が挑戦。また、呉清源は戦後の混乱期から碁を捨てていたので、本因坊戦の予選に参加もしませんでした。以降、呉は本因坊戦に参加せず、後に本因坊取得者と毎年特別3番碁を打つことになります。
第4期の薫和木谷戦は、先番4目半コミ出しの五番勝負となり、「豆まき碁」といわれた軽妙な薫和の石運びに破れ、薫和は本因坊連覇を果たします。
第5期は、本因坊奪還を目指す橋本宇太郎が挑戦者となりますが、この当時、関西在住の棋士が挑戦者となることには大きな意義がありました。
日本棋院の創設時に関西支部が組織され、関西だけで独自に昇段手合が行われていたものの、五段以上の昇段は認められず、東京の大手合に参加する場合でも資格審査が必要でした。したがって、有望棋士の多くは必然東京に移籍することになり、関西支部は下部組織的な存在でしかありませんでした。
その後、関西支部は、関西別院、関西本部と改称しましたが、その実態、待遇はほとんど変わりません。
これまで、対局の都度上京したり、待遇面でも何かと東京の棋士の下に扱われており、改善を求めて昭和23年大阪府から財団法人の認可を受けて関西棋院と改称します。
両棋院で最も対立が深まったのは、戦争で焼失した日本棋院の新会館再建の寄付集めをはじめたときです。関西にもノルマを課し、東京の会館設立と関西のために使用する分と折半する約束でしたが、関西でスポンサーとなってもらった財界人に、『東京の会館のために寄付をしたのではない』と言われ、全額を地元関西の新会館設立にあててしまいました。
こうした仲で、橋本は関西の全棋士の「扱いは下でも実力は同じだ」という期待を背負っての挑戦手合となり、薫和との七番勝負を4連勝、見事に本因坊返り咲きを果たします。
しかし、その就位式の祝辞で日本棋院理事長が「本因坊戦はこれまでの1期2年から時代の流れに沿って1年の開催に改めたい」と発言したことが波紋を呼びます。
関係者にしてみれば、これまでの勝負はコミの有り無しや、何番勝負にするかなど毎期対局規定が定まっていないことを改善し、1期1年のサイクルのほうが日程もわかりやすく、ルールの統一の一環として発言したもので、関西棋院の役員にも話してあったので、当然橋本にも伝わっていると思ったかもしれません。その上、橋本自身が「予選期間が長すぎる。開催は1期1年」と主張していたこともあって、問題は起きないと思ったかもしれません。
しかし、自分の主張することとは関係なく、橋本にとっては晴れの就位式で、本因坊である自分に事前の話もなく変更を発表するとは、サイクルを早めてでも関西から本因坊を取り返したいのかと受け取らざるを得ませんでした。
この一件により、橋本を中心に関西棋院は理事会を開き、独立派と日本棋院協調派に分裂。独立派は橋本を中心に、独立組織としての関西棋院を宣言し、協調派は日本棋院の協力により関西総本部を設立します。
そこで問題となったのは、本因坊の名跡を関西棋院の棋士が保持していることです。
関西棋院の存続・安定の基礎を築くためには、本因坊の看板は絶対に必要なものであり、これが日本棋院との交渉材料にもなりました。
次期の本因坊戦予選に関西棋院所属棋士を参加させなければ、次の挑戦手合に応じないという構えの橋本に対し、本因坊の名跡は「日本棋院所属棋士による選手権」であるから、脱退した橋本から本因坊を剥奪すべしという意見が出されましたが、結局は実力で取り返さなければ意味がなく、関西棋院の存在を一時的にせよ認めざるを得なかったのです。
坂田の苦汁 第6期、橋本から本因坊奪還の至上命令を受けて挑戦者に名乗りを挙げたのは31歳の若き天才坂田栄男。坂田は日本棋院総員の期待に応えて4局めまで3勝1敗、碁の内容でも圧倒していました。
第5局、山梨県昇仙峡の対局では、橋本の「首を洗ってきました」という対局前の挨拶から、坂田は気持ちの浮つきを抑えられず急所の1局を落とします。
続く第6局は、橋本の「負けるとしても細かくなるようにと思っていた」という言葉のように、橋本の辛抱が勝利を呼びます。
最終局となった第7局は、坂田の好局。中盤橋本にただダメをつながらせるだけの手を打たせ、自分に14目の大きな手を残した局面、坂田は「我勝てり。」と本因坊になった後のことを考えたことが若さゆえの失敗と、後に自ら認めているように、負けるように負けるように打ち、ついに3連敗を喫し、逆転で橋本の本因坊防衛を許します。
坂田優勢の時には、現場に居合わせた関西棋院の棋士から日本棋院のの理事に「関西棋院は橋本先生の独裁で長く持ちそうもない。復帰したいので、そのときはよろしく」と、挨拶に立ち回る者もいましたが、橋本勝ちとなると、そんな言葉を発したことも忘れて総出で大喜びしました。
坂田は、翌期以降は本因坊の挑戦者にさえなることができず、次に檜舞台にあがるまで10年を要することになるのでした。
また、橋本はもう1年本因坊を名乗ることができ、この間に関西棋院は完全に足場を固めることができました。もし、この年に坂田に本因坊を奪われていたら、関西棋院は自然消滅し日本棋院に復帰せざるを得なかったでしょう。
秀格の9連覇(前半) 第7期は、予選の開催が4ヶ月も遅れてしまいました。これは、関西棋院の棋士の参加を認めるかどうかで揉めたためです。前期、橋本が坂田の挑戦を受ける条件として「今後も関西棋院の参加を認めること」を主張していました。最終的にはこの約束がものを言って、関西棋院から本因坊である橋本の他に6名の参加が認められることになりました。
本戦リーグは大混戦となり、7名のうち5名が4勝2敗で並び、改めてトーナメント戦が行われます。そうして挑戦手合に登場するのは高川格と決まったとき、日本棋院関係者は、「坂田でだめだったものを、高川では」と、半ば諦め気分でした。
新聞購読者の勝敗予想投票も8対2で橋本、という結果でした。
第1局で高川は、尻抜けの見損じ(自分の石が取られて連絡していることを見落として取りに行った)で破れ、周囲を落胆させます。
しかし、当の高川本人は、自分なりにこの碁を分析し、内容自体は悪くない。自分でも本因坊に十分対抗できると、自信を深めていました。
そして、第2局からは自らの棋風、後に平明高川・ボウシの高川と言われるようにゆっくと少しずつコミにかけ、形勢を自分のものにする打ち方で勝利をものにしていきます。対局後、橋本が「あんな手で追いつくのか?ぬるま湯につかっているようで、どうも調子が合わない」とこぼすように、高川の四連勝でついに本因坊を奪取し、本因坊秀格を名乗ります。
また、この期から、本因坊と呉清源の3番碁が始まります。高川は本因坊戦挑戦手合を戦って疲れた後にこの3番碁を毎期打っていました。対局料が、本因坊戦の1局3万円に対し、20万円と破格ではありましたが、高川本人が「なんで、挑戦手合でヘトヘトに疲れている時期に打たせるのか」とこぼしたように、毎期呉に3番ずつ負け続けて、11連敗を喫します。ただし、その後4連勝と少し押し返すことはできました。
次の第8期もなかなか予選がはじめられませんでした。これは、関西棋院の新五段3名の参加を「昇段規定が違う。日本棋院の五段と同等とは認めない」と日本棋院側がクレームをつけたことにあります。
この当時、本因坊戦はまだ低段者は予選の参加がきでませんでしたので、関西の棋士に五段の資格があるかどうかが議論となった末、日本棋院の五段と審査手合を行い、その結果で決めようということになります。ただし、この手合は日本棋院が勝手に審査だというのであり、関西棋院は予選の一部だと思っていて、結果については公表しないという約束でした。
そして、関西棋院側が勝利を収め、ようやく予選が開始されます。
第8期は、木谷實と坂田栄男が6勝1敗となり、プレーオフの結果、悲願の本因坊を目指す木谷實が第4期以来2度めの挑戦をします。
このときの新聞読者の勝敗予想は木谷勝が65%。高川は前回よりも自分の評価が少し上がったこともあり、別段予想は気にしないふうでした。また、勝敗予想座談会で前田陳爾が「高川さんにはタヌキ的な要素があるから(勝敗はなんとも言えない)」と発言したことから、後年、弱いフリをして勝負をひっくり返す「タヌキ」の異名がつけられるのでした。
高川は、今度は同じ日本棋院同士、しかも先輩の木谷であることからリラックスして戦うことができ、見事に4勝2敗で防衛を果たします。
次の第9期も、またまた開催が遅れます。同じく関西棋院の棋士の段位を認めるかどうかという問題ですが、この期は18歳で六段に上り天才と言われた橋本昌二について、昨年は四段で今年は一足飛びに六段とは無理な昇段だということでした。
橋本昌二にについては、棋譜審査をしようということになり、日本棋院の長老鈴木為次郎八段によって調べられた結果、十分な棋力と認められてようやく予選が開始されます。その橋本昌二は、予選で元本因坊の岩本薫を白番で破るなど、確かな実力を示すことができました。
第9期の挑戦者は杉内雅男、尚、この期木谷實はクモ膜下出血により欠場となりました。
この期は、高川自身が「9連覇中もっとも危なかった」と言っています。第4局まで互いに黒番勝ちで2勝2敗。第5局で高川は大石の死活の場面で1手パスのような手を打ち、いつ投げようかと思っているうちに、杉内のミスのお返しがあり辛勝。続く第6局も杉内が優勢から緩み、逆転勝ち。内容的には杉内の4勝2敗でもおかしくないものでした。
高川は、第9期の防衛を「初めての年下からの挑戦を退けて新しい自信がわいてきた。勝負のひとつの節目になったと思う」と述べています。
第10期は「忍の棋道」といわれ、渋い芸風の島村利博と宮下秀洋のプレーオフとなり、島村の挑戦。
戦前の予想は相変わらず高川の不利でしたが、勝負は意外にも高川の4連勝で幕となります。
3局目までは島村にも十分に勝つチャンスがあり、内容は勝敗ほど一方的ではありませんでした。
しかし、4局目は島村の完敗。その理由は、対局の前夜祭で、立会人を務める先輩棋士が島村を元気付けるために酒宴を開き、酔った勢いで島村を抱えあげたところ誤って落としたために腰を痛めてしまったのでした。
秀格の9連覇(後半) 第11期は、画期的な改革の行われた年となりました。
これまで、予選参加資格を五段以上の高段者としていたものを、日本棋院の全棋士すなわち初段から予選に参加できるように改正されました。高段棋士の中にはまだ「低段者の出る幕ではない」という意識を持つものもいましたが、「全日本選手権」である以上は全棋士参加が当然と、主催者の意向として押し切りました。
また、これまで毎回問題になっていた関西棋院の段位承認問題について、日本棋院と最終予選で合同するときに、関西棋院から選抜された7名を加える、ということに決められました。そして、その参加人数は、本戦リーグで関西棋院の棋士の勝敗によって増減すると定められます。
リーグ戦で関西棋院の棋士が1勝すると0.5ポイント、1敗するとマイナス0.5ポイント。リーグ終了時に1ポイントごとに参加者を1人増減するものでした。
この方式は最初のうちこそ励みになりましたが、ある時期、関西棋院側の大不調により、参加者がどんどん減らされ、ついに予選参加枠が1名になってしまいました。もし0になればその後は関西棋院の参加ができないということになってしまいます。そこで改めて制度を改定し、予選32名中、日本棋院28名、関西棋院4名に固定されることになりました。
比率7対1は、現在でも有効ですが、他の多くの棋戦が両棋院の棋士人数比率に合わせた3対1を標準としていることから、本因坊戦はペナルティをいまだに抱えているといえます。
さて、第11期は島村利博の連続挑戦となりました。前期は4連敗と敗退しましたが、この期は他の棋戦でも好調で、島村有利ではないかとまた戦前予想が立てられます。本因坊4連覇をしてもなお、高川の強さは認識されていませんでした。
高川は、初めて1勝2敗と相手にリードを許しながら、しぶとく3連勝で防衛。5連覇を果たします。
この5連覇を偉業と認めて名誉本因坊の規約が新設され、引退後は名誉本因坊を名乗る資格が与えられます。
尚、高川は9連覇まで伸ばしたことにより日本棋院創立40周年のときに現役のまま名誉本因坊を名乗ることを認められ、また現在では名誉本因坊の規約は、二十一世本因坊秀哉の後の世系を継ぐことが定められ、二十二世本因坊秀格となっています。
第12期の挑戦は藤沢朋斎。藤沢は、4年前に呉清源との2度の十番碁に敗れて先に打ち込まれた不成績の責任感から日本棋院を脱退していました。
藤沢は、時間を目いっぱい使って最強の手を選ぶ棋風で、高川といっしょに秒読みという敵とも戦わなければなりませんでした。
第4局では、序盤で高川の大石を殺しながら、高川が投げずに打ち続けるうちにおかしな手を連発して逆転。最終となった第6局でも、コウを謝ってついでおけばはっきりと勝ちだったのに、無理に仕掛けて逆転負け、と不運がつきまとい、またも4勝2敗で高川の6連覇となりました。
第13期は木谷、坂田、杉内の3者同率となり、プレーオフトーナメントが打たれます。3人なので、1人が不戦勝。坂田は自分はクジ運が悪いので1局よけいに打つ割を食うのはいやだとしり込み。また、木谷も以前プレーオフで坂田と1局よけいに打った経験がありクジを引きたくないふうでした。
そこで、杉内が「じゃぁ僕が先に引きましょう」とさっと不戦勝のくじを引き当ててしまいました。結局、気分的にハンデを負った坂田は木谷に勝ったものの、杉内に破れ、杉内2度目の挑戦となります。
このころになって、ようやく戦前予想が5分5分。高川3勝2敗で迎えた6局めは、杉内の半目勝ちが見えたと思った瞬間、杉内は放り込みのコウを避けて1手手入れをしたため、高川の逆転半目勝ち。7連覇となります。
第14期は、木谷實の登場で、いよいよ高川危うしの声が大きくなりました。戦前予想座談会では「あらゆる面で木谷が上。勝負は一方的」と断言されるほどでした。
しかし、木谷の問題は健康面にありました。数年前クモ膜下出血による欠場以来、高血圧、年齢による体力の衰えなど、七番勝負の長丁場に耐えられる体力かどうかが心配されました。
4局まで2勝2敗でしたが、高川の負けた2局は完敗。勝った碁は辛抱しての粘り勝ち。木谷の気力もここまで、5、6局では内容がガタガタになり、これで高川8連覇。
いつしか「高川のタヌキに化かされた」などと揶揄されるようになるのを最も如実に示したのは、第15期、藤沢秀行の挑戦を受けた年の第4局。
形勢は悪く、これに負けると1勝3敗の角番に追い詰められるという状況で、中盤のコウ争いが起こります。そこで高川が無コウを打ち、それを藤沢が手拍子で受けてしまいます。それでもまだ藤沢の形勢は悪くなかったのですが、すぐに無コウであったことに気がついてしまった藤沢が気分を腐らせて逆転勝ち。5、6局も藤沢は立ち直れず、またも高川の防衛。「わざと藤沢の手拍子を誘い心理戦にもちこんだ高川はやっぱりタヌキだ」という声もあがりました。高川は「あの無コウは、本当に自分の勘違い」といい、その事実はヤミの中。
高川が9連覇を果たす間、坂田は本因坊戦以外では抜群の成績を上げ、他棋戦で高川と当たったときにも圧倒的に勝ち越していました。
本因坊戦では挑戦者にさえなれず、坂田は半ばヤケクソ気味に「高川さんが10年目になったときに、私が挑戦して止める。」と宣言し、それが実現します。
栄寿独占の時代 坂田は、第6期以来本因坊戦の挑戦者にさえなれませんでしたが、他の棋戦で高川と何度か対戦し、坂田対高川は坂田が7割を超える勝率で圧倒していました。ただし、高川は勝率は悪くとも棋戦本戦や重要な対局では五分に戦っており、いまや勝敗予測のつかない好勝負が期待されました。
挑戦手合前の心境を「10年目に待ち焦がれた恋人の登場ですね」と問われ、高川は「10年目に巡り会った、最も相性の悪い恋人です」と言い返しました。
9連覇中、細かいヨセの勝負になれば高川のペースといわれ、勝ち続けてきましたが、この期、以外にも坂田に細かい碁を勝ちきられ、2度の半目負けを喫し、「すべての面で坂田が上をいった」と、ついに坂田が念願をかなえ、本因坊栄寿を名乗ります。
坂田が始めて本因坊に就いたのは41歳。現代の棋士が20代でトップに立つのに比べ遅咲きといえます。
当時はまだ棋聖戦、名人戦はなく、棋戦総数が少なかった時代に40代でようやく本因坊に就きながら、最終的に獲得タイトルが64(趙治勲に抜かれるまで長く1位でした)は驚異的な数字であり、如何に全盛期に勝ちまくったかがわかります。
第17期の挑戦者は半田道玄、久々に関西棋院の登場となります。
半田は、坂田との対戦成績で勝ち越している数少ない棋士のひとりで、坂田も苦戦するかと思われましたが、4勝1敗で圧倒します。
第18期は高川の挑戦。高川は本因坊在位中はどんなに連覇しても評価が低かったのに、本因坊を失ってから「実は高川は強かった」と言われるようになっていました。
勝負は第4局まで2勝2敗。高川には妙な記録があって、9連覇中6回が2勝2敗から2連勝。また、9度中8度は相手を角番に追いつめると足踏みすることなく勝ちきっていました。
坂田はそういったジンクスを気にする性質であり、5局めを負けると高川のパターンだと信じ、必死の思い出5、6局を連勝して3連覇を果たします。
また、同じ年、第2期名人戦では、藤沢秀行名人を4-3で下し、秀哉以来の本因坊名人となりました。
その翌年は、坂田にとって最高の年となり、年間成績30勝2敗。本因坊・名人・王座・プロ十傑戦1位・日本棋院選手権・NHK杯・日本棋院1位と、十段を除く7冠を制覇。その年に第19期本因坊連続挑戦となった高川を4-0で圧勝。
その後、第20期挑戦者山部俊郎、第21期挑戦者藤沢秀行を、続けて4-0で退け、18期の第5局から始まった本因坊挑戦手合での連勝は、第22期林海峰に3連勝するまで、通算17連勝まで伸ばします。
しかし、本因坊では連覇を続けたものの、第2期3期と連覇した名人位は第4期に坂田の2まわりも年下の挑戦者、林海峰に奪われていました。
名人戦では林海峰の力を見くびっていた。本因坊戦ではそうはいかない、と、第22期の林の挑戦を退け、本因坊7連覇を果たしますが、翌期、再び挑戦者となった林海峰に、ついに最後の牙城を明渡すことになります。
林海峰から木谷一門へ 絶頂の坂田を追う一番手は、坂田より二廻りも若い林海峰でした。本因坊戦より前に名人の挑戦者となり、坂田は「20代の名人など有り得ない」と言い放ちましたが、対局を重ねるうちに「どんなに形勢が悪くても平然としている。こちらが何か勘違いしているのかと疑心暗鬼になる」と次第に調子を崩して行き、自滅するように名人を明け渡してしまいます。
続いて林は第22期本因坊戦でも挑戦者として登場します。坂田は一度はこれを退け、最後の牙城を守り通しますが、その翌年第23期も林は連続して挑戦者となり、その最終局で、坂田はコウによる大石の切断の手段を見ていながら、平然とした態度の林を見てコウに行くタイミングを見切れずに破れ、本因坊を明け渡してしまいます。坂田は「コウに行けば勝っていた」と一晩中悔やみました。
第24期、林海峰によって一気に世代交代した本因坊戦で新たに挑戦者になったのは、四段でリーグ入りの記録を作った加藤正夫五段。結果こそ林の防衛でしたが、多くの若手棋士は、同世代の仲間の活躍を見て、自分たちでも十分トップ棋士と戦えると自信を持つようになりました。
第25期、挑戦者とした坂田を4連勝で下し、林の時代が続くかというところに割って入るのが、石田芳夫。
「林さんの、いったいどこが強いのですか」と言い放ち、言葉のとおり本因坊を奪取。木谷一門の俊英は一気に開花し、およそ30年間本因坊は着たに門下の争いになります。
名人本因坊時代の林は、二枚腰と呼ばれ、容易に負けない終盤の力に定評がありました。一方石田はコンピュータと呼ばれ、正確無比なヨセの大小の見極めと計算力があり、林に「中盤までに相当引き離さないと勝てる気がしない」とまで言わせるほどでした。
林は、自分が坂田から順にタイトルを奪ったように、今度は石田に奪われていくことになるのでした。
コンピュータ・宇宙流・殺し屋 木谷實は、ついに名人、本因坊に縁がありませんでしたが、その夢は一門の優秀な弟子たちによって叶えられました。
林から本因坊を奪った石田芳夫は、半目差まで読みきる正確なヨセと計算力でコンピュータと呼ばれ、名人も林海峰から奪取して、坂田・林に続く3人目の名人本因坊となり、本因坊5連覇を果たします。
林、石田と、終盤力(ヨセ)に定評のある本因坊が続いた後、挑戦者として登場したのは木谷一門から武宮正樹。常に中央に大模様を目指す宇宙流と呼ばれた棋風は、本因坊初挑戦のときこそ石田に押さえ込まれましたが、2年後に再挑戦して、計算の立たない碁盤の中央に向かう感覚の世界での勝負に持ち込み、本因坊を奪取します。
武宮に続くのは、また木谷門から強烈な個性的棋風を持った加藤正夫。多くの専門棋士が「相手の弱石は攻めて得をして引き上げる」という攻め損ないのリスクを回避した打ち方をするのに対して、加藤は「相手の弱い石を取れると判断したら取りに行く」という直接的な棋風で「殺し屋」と呼ばれました。
この時期のあらゆるタイトル戦は、木谷一門三羽烏と言われた石田・加藤・武宮と、その先輩格の大竹英雄、反対に若い才能から小林光一、趙治勲たちの寡占状態であり、唯一、林海峰がタイトル独占阻止に割って入るのみでした。
つづく