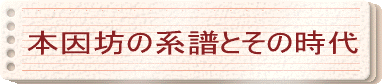 �@�@�Z������G�Ƃ܂��@
�@�@�Z������G�Ƃ܂��@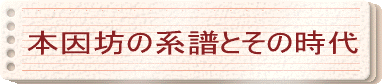 �@�@�Z������G�Ƃ܂��@
�@�@�Z������G�Ƃ܂��@
�J�c�@�Z���@�@���y���R���㒆���A�����̌�łōŋ��Ƃ��Ēm���Ă������l�̐��ɋ����������@�@�̑m�E���C�́A�Ⴍ���ĖL���ȍ˔\�������A20�̂Ƃ��ɐ��̒���ŐD�c�M���ɉy�����܂����B�M���͑m�������ł������A���C�̌�|��F�߉��x����̐ȂɌĂ��悤�ɂȂ�܂��B
�{�\���̕ς̒��O�A�M������O�œ��C�͗���(�щƂ̌��c�Ƃ����Ă��܂�)�Ƒǂ��ĂR�R�E�������ƂȂ������߁A�R�R�E�͕s�g�̑O���Ƃ����`��������܂����A����͂ǂ������b�̂悤�ł��B�������A���C���M���ɋC�ɓ����Ă����͎̂����̂悤�ŁA�M���́u���C�����܂��Ƃ̖��l�v�ƖJ�߁A���ꂪ�u���l�v�̌ď̂̋N�����Ƃ������Ă��܂��B
�M���ɑ����ĖL�b�G�g�ɂ��]���A��̎w����߁A����ɍ]�ˎ���ɓ����Ă͉ƍN�ɂ��d���邱�ƂɂȂ��������͂͑傢�ɕ]�������Ƃ���ł����A��ŏO�Ə����w�O�{�̌��E�Ƃ��ĔF�߂����A�}��������ƌ����x���m�������邱�ƂɂȂ������т͔��ɑ傫�Ȃ��̂�����܂��B
���C�͋��s������ɂ���{���V�Ƃ��������ɏZ���Ƃ���A���̖�������ČĂꂽ�ƌ����Ă��܂����A���ۂɎ�����ɂ��̂悤�ȓ������������Ƃ����L�^�������܂��ł��B�{���V���l�̐��Ƃ��Ĉ������ŏ��́A�V���\�Z(1588)�N�A�G�g���Â�����O�����ɗD���������C�ɗ^�������ɋL����Ă��܂��B���ۂɓ��C���{���V�𖼏��̂́A�c����(1603)�N�ƍN���]�˖��{���J���A�A�{����Ƃ��Ɍ�̎w����ł�����C��������A��A�������_�Ƃ�����������܂����A������ɂ��Ă����łƂ��͖{���V�����R�ƒʂ薼�ƂȂ�A�]�˖��{����\�����鎞�_�ł͎���{���V�𐩂Ƃ��Ă����悤�ł��B
�܂��A���̑��ɂ��`���͑����A�����w�O�̏��㖼�l�E�勴�@�j�́A�Z���̏����̒�q�ł��������A�Z����l�Ō鏫���̗����𑩂˂�̂͌��͏W���ł悭�Ȃ��Ƃ��āA�����Ɋւ��Ă͏@�j�Ɉς˂��Ƃ�����������܂��B���ۂɁA�@�j�ƎZ���̏�������ǂ̊������c����Ă��܂����A�L�^�ɂ��Ə@�j�̂ق����N���ł���A���͓I�ɎZ���̒�q�Ƃ����͍̂l���ɂ����悤�ł��B
���l�Ƃ��č]�˖��{�����ŏO�𑩂˂�鏊���������Ƃ����b���A�ŋ߂̌����ł́A�鏊�͖��{�̔C���ł͂Ȃ��A��ŏO���m�Ō��肵���n�ʂ�����ɖ����A���{�Ȃ������Е�s������ŏO��������̂ɓs�����悢�̂ŖٔF���Ă����炵���Ƃ������Ƃł��B
�Z���́A��Ɋւ��邱�ƈȊO�ɂ͎c���ꂽ�L�^�����Ȃ��A���̌�łȂ���\�Όܐl�}���̂ق��ɁA������ŎO�S�ƍ]�˂ɏZ��������������Ă��邱�Ƃ���A���{�̉B���ڕt���A���V�B���������̂ł͂Ȃ����Ƃ�����������܂��B�M���E�G�g�E�ƍN�ɂ��ꂼ��d���������͂ƁA��łƂ��ĕ��ƁA���l�o���ƌq���肪����A�o����̏��l������₷�������Ƃ������������āA�����l����ꂽ�̂ł��傤�B
�Z���ɂ͎c���ꂽ������20�ǒ��x�����Ȃ��A�ΐ푊��͑S�ė����Ɍ����Ă��܂��B�������A�Ō�܂ŋL�^���ꂽ���̂͂P�ǂ����A���Ƃ͂��ׂ�120�`130��ŋL�^���I����Ă��܂��B���͓I�ɂ͋Z�p�̖��J��Ȏ���̂��߂ɁA�㐢�ɗ�邱�Ƃ͂�ނ����Ȃ����Ƃ̂悤�ł��B
�@�Z�x�@�@�Z���ɂ͎Z�ׂƂ�����q�����Ė{���V�p������\��ł������A�Z�ׂ��S���Ȃ������߁A��q�̒������ׁi���ƊJ�c�j�Ɍ鏊�Ƃ��Ă̑S��������A�{���V�Ƃ͈ꎞ�r�₦�܂��B�A���鏊���p������ɂ������āA���̂Ȃ��ŗL�]�ƌ�����Z�x�Ƃ�����q�ׂɑ����A�b���Ă��̂ɂȂ�悤�Ȃ�{���V�Ƃ��p�����čċ�������悤�ɓ`���܂��B���ׂ��t�̈⌾��ǂ����A�Z�x����ĂĖ{���V�Ƃ������܂����B
���ׂ͂͂�����ƎZ���Ɍ�����ׂ�i���邢�͂���ȏ�́j���͂ł��������߁A���l�ɐ�����鏊�ƂȂ�܂������A���ׂ͌鏊�̌���p���҂��w�����܂���ł����B�ˏo�������͂��������҂����Ȃ��������ƁA�Z�x�����������Ƃ͂����A�܂��鏊�ɂ���ɂ͎�N���������Ƃ��������悤�ł��B���ׂ��S���Ȃ��Ă���10�N�Ԍ鏊�s�݂̎��オ�����܂������A��ʂ̒����Ɍ�ォ��鏊���p�ɂ��ĉƌ��S���o�Ȃ̂����F�c�������Ȃ��܂����B
�������V�i�̈���ƈꐢ�Z�N�i�ÎZ�N�j���u���͂͂Ƃ������A�ł��N���҂ł��鎩���ɔC���Ăق����v�Ɛ\������܂������A�u���͂��Ȃ����̂��鏊�ɏA���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ƒނ����܂��B�I���Ȏ��E�ɕs�������o�����̂�������܂���B
�����ŁA���͏����猾���āA�{���V�Z�x�ƈ����ׂŏ�������悤�Őf����܂����A���ׂ́u�Z�x�͓��t�̂̓����q�ł���A����ɑ�t���Z���̐Ռp���B�����͎��ނ���v�ƒf��A�Ⴂ�Z�x���������������߂Ȃ��������߁A����ɂ��炭�鏊�̋�ʂ������܂��B
���̂S�N��ɁA�Z�x�ƈ���Z�m�̘Z�Ԍ�ɂ��鏊�����肷��悤�ɍ���������A�N�ɂP�x�̌���̏����ŋ�N�i�r��3�N�Ԍ���̋x�~������܂����j�Ƃ����������Ƃ����y�[�X�ōs���܂������A�݂��ɐ�Ԃ������Č��������Ȃ��������߁A�܂����鏊�͎����z���ƂȂ�܂��B
�N�ɂP��̏�����Ƃ����I���ȑǂɂِ͈�������܂��B
����́A�{�����Ƃ��ẮA�Z���Ɠ��ׂ̌n��ł���{���V���鏊�ɏA�����������̂ł����A�V�C�m�����Z�m���ۛ��ł��������߂ɂȂ��Ȃ��i�߂邱�Ƃ��ł����A�V�C���S���Ȃ��Ă��炢�悢��Z�x���鏊�ɏA���悤�Ƃ����̂ł����A�Z�m�Ƃ��̌㉇�҂ł���V���ۉȐ��V��̔��ɂ����܂����B
�u�Ȃ�Έ�ԏ��������Ă݂�v�Ɩ����܂������A�Z�m�������������߂ɁA���N�A�܂����N�A�ƎZ�x���Ȃ�Ƃ������z���Ȃ����A�ƌJ��Ԃ����ƂɂȂ��Ă��܂����A�Ƃ������̂ł��B���̂܂܂ł͋t�ɎZ�m�ɑł����܂�Ă��܂��ƐS�z���āA�T�ǖڂƂU�ǖڂ̊Ԃɋx�~���Ԃ����A�Ō�ɎZ�x�����������_�Ō鏊�̘b�͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃɂ����Ƃ������̂ł��B
���̂Ƃ��̎Z�m�̔�������ǂ͖{���V�ƂɈ⍦���c�����ƂɂȂ�܂����A����͎��̂��b�B
�O�� ���x �Z�x�ƎZ�m�̋�N�ɓn�鏟���̌�A�鏊�ɂ��Ă������~�݂ƂȂ�A�Ղ��p�������x�́A�V���Ɍ鏊��ڎw���Ă��܂����B
�������A����Ƃ��ˑR����Z�m�����{�̉����ɂ�薼�l�鏊�ɂȂ�ƒm�炳��܂��B�m���ɎZ�m�͓����̎��͍ō��ʂł͂���܂����B���x���Z�m��j��Ȃ���Ό鏊�ւ̓��͖����ƔF�����Ă��܂������A���x������ɏo�d���Ă��Z�m�Ƃ̑ǂ͂Ȃ��A���x�̑���͂����ƎZ�m�̒�q�Z�N�����߂Ă��܂����B�Z�m�Ƃ̑ǂ��K�킸�A�{���V�Ɠ���ƈ���ƐՖڂ��ǂ���̂ł́A��ɖ{���V�Ƃ���i���Ɍ����Ă���悤�ȕs���������Ă��܂����B
���̎Z�m�����x�͎����Ƒǂ��Ȃ��܂ܖ��l�ɂȂ邱�Ƃ͓��x�ɂ͔F�ߓ�A����̌���Ɉًc�������܂��B�u�����������ė~�����B������Ζ����ɔw�����Ƃ��ė��Y�ɂȂ��Ă��悢�v�Ƃ̊o��������Ċ肢�͎�����܂��B
����́A�O�̂悤��1�N1�ԂȂǂƂ���������肵�����̂ł͂Ȃ��A1�N��20�Ԃ��A3�N60�Ԍ�ɂď���������悤�������܂��B�Z�m�͂������l�i�ɖ������Ă���̂Ŏ荇�͓��x�̐�B���x�̖ڕW�́A�Z�ԏ����z���Đ�ݐ�Ɏ荇���A�u���̌�����ێ��ł��Ȃ��̂ł���Ζ��l��ނ��ׂ��v�Ǝ咣���邱�Ƃɂ���܂����B
�������A���Ȃ炷���ɑł�����ł݂���Ƃ����ӋC���݂Ɨ����ɁA���߂̂����͎Z�m���P�킵�čŏ��̔N��12�Ԃ��I������Ƃ���Łi1�N20�Ԃ̃y�[�X�͖���������i�s���x��܂����j�A���x5���Z�m3��4�W�R�ƁA�傫�ȍ��͂��܂���ł����B���҂Ƃ��ŏ���20�Ԃ����肾�ƍl���Ă���A�����܂łɎ荇�������Ȃ���u��͑ł��Ȃ��Ă��Z�m�Ɍ鏊��C����悢�ł͂Ȃ����v�Ƃ������͋C�ɐ��肩�˂Ȃ��Ɠ��x�͏ł���o���܂��B
�����œ��x�́A���������˔\������Ƒf���ɔF�߂Ă���{���V�Ֆړ���Ƒ��k���A����̎�@���̗p����悤�ɂȂ��Ă���S�A���A�X���R�s�S�W�S�ƂȂ�摊��ɑł����݂��Ȃ�܂����B
�|����̈Ӓn��ʂ����Ƃ��ł������x�́A�⍦�������A�����ɎZ�m�̖��l�鏊����������~�낳���ɁA�ł�����͖��N�̌���̂P�ǂ��̃y�[�X�ɂȂ�A����̓�\�Ԃ�ł��I�����Ƃ���Œ��f���āA���Ƃ͎Z�m�����R�ƑމB����̂�҂��ƂɂȂ�܂����B�Z�m���鏊��ނ������Ƃ��A���x�͌��ɋt��������Ƃɉ������Ď���������Ė��l�ɂȂ낤�Ƃ͂��܂���ł����B���x�̂��Ƃɂ͓�����A�{���V�Ƃ̈��ׂ�����Ă������Ƃ��������ł��傤�B
����ɂ��Ă̕]���́A�V��̎Z�m���ł�����̓��x�̒���16�Ԃ܂ł��悭�������������Ƃɂ��A�Z�m�̂ق��Ɉ���̒����������Ƃ����܂��B�܂��āA���x�̌��ɓ����ẮA�Z�m�������ł��ł��Ȃ������ł��傤�B
�l�� ���� �@�@�u�芄�v�̗��_�I�Ȋ�b�͓���n�܂����ƌ����܂��B����̕z�Η��_�A�̐A���Ր헪�́A�����ǂ̌�ł��ɂ������Ă��Ȃ��������̂�������l�������Ă����Ƃ܂Ō����Ă��ߌ��ł͂���܂���B���̓ǂ݂̐[�����͌���̈ꗬ���m���Ϗ܂��Ă������ɂ͗����ł��Ȃ��قǍ��x�Ȏ�ł��ӂ�Ă��܂��B
�����悢�於�l���肢�o��Ƃ��ɁA���ƂƂ̎荇���т�Y���܂������A�قƂ�ǂ̑�����悩����ɑł������Ă��܂����̂ŁA���Ƃ��當��̂��悤������܂���ł����B�����l�鏊�ƂȂ��Ă���̊��Ԃ́A����ȊO�ł��ƌ��Ԃ̌𗬑ǂ�����ɂȂ�A�������Ƃ���ɑR����e�Ƃ̌��r�ɂ���āA��E�S�̂����x���A�b�v�����Ƃ�����ł��傤�B
����N�ɁA�����g�߂̗��K�ɂ��荇�����߂��A����͌��S�q�ŕ��ӂ��܂����A�A���ɍۂ��ĖƏ�����߂��āA���i���i�j�ɓ�q�A���Ȃ킿�O�i�i�̖Ə�s���܂����B����ɂ��Γ��g�͎��i���ɓ�q�u������v�Z�ɂȂ�\��i�i�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B�����͊Â��i�ʂ������̂�������܂��A������������A����͎����̗͂����ۂɂ��̂��炢�Ɍ��Ă����̂ł��傤���B���������Ă������x���Ȃ��قǎ��͔͂�����o�Ă��܂����B
����ɂ́u�܌Ձv�ƌĂ�A���͓I�ɂ͓���ɔ���T�l�̒�q�i���I�E���߁E�E�{�ׁE���ׁj�����܂����B���̒��ŁA���߂͓���ƂP�ΈႢ�ł��������߁A�{���V�Ƃ̐Ֆڂɂ͐������Ɉ��Ƃ��p�����A���I��V��̐ՖڂƂ��܂����B�������A���I�͑������A���ɍĐՖڂƂ��������l�ɑ����B���̖{�ׁA���ׂ�20��ŖS���Ȃ�A����͗L�]�Ȓ�q�����ׂĎ����Ă��܂��܂��B
�ӔN�A���̒��O�܂Ŗ{���V�Ƃ̐Ռp����I�т܂���ł������A�a���ň��Ƒ��Ƃ̓�����W�߂āA�Ō�̔鑠��q�i���q�A�B���q�Ƃ��`������j���m�ɖ{���V�Ƃ̑S�Ă�����A���Ƃ��p���������߂ɂ́u���m�𖼐l�鏊�ɏA������悤�b�B���Ăق����B�܂��A���ߎ��g�͌鏊��]�܂ʂ悤�Ɂv�Ɩ����܂����B
�Ֆ� ���I �@�@13�Ŏl�i�A16�ɂ��Ċ��Ɏt�̓���ɔ�����͂̂������j��ō��̓V�ˊ��m�B�c���ꂽ�����͑�������܂��A����ƌݐ�Q�Ԃ�ł��A���ɍ��ԂP�ڏ����ƂȂ�ȂǁA���̎��͕]���͍������̂�����܂��B
�ՖڂƂȂ�����ł��ƂɂȂ����Ƃ��A���Ƃ���u�i���Ⴗ����B���͂͂����Əゾ�v�ƈٗ�̃N���[���������邱�Ƃ�����܂����B�{���A���Ƃ̂��̂����i���邱�Ƃɕq���ɂȂ���̂ł����A�Ⴗ����Ƃ�����ȂǁA�܂��l�����Ȃ����Ƃł����B
�����́A������z���Ăǂ��܂ŋ����Ȃ邩�Ɗ��҂���܂������A�c�O�Ȃ��狹��������22�̎Ⴓ�ő������܂����B
�ܐ� ���m�@ ����́A�D�G�Ȓ�q��S�Ď����A���̌�͐Ֆڂ��߂Ȃ��܂܂ł������A���̒��O�ɂȂ��Ă���A�{���V�Ƃɓ��債�������13�̓��m�Ɍ���p�����܂��B���m�͖{���V�Ƃɓ��傷��ȑO�̏o�����s���ŁA����ɂ͓���̎��q�i�B���q�j�������Ƃ������Ă��܂��B����̈⌾�ɂ��A���i���߁j���ׂɂ��b�����A���l�鏊��ڎw���܂����A������ɍD�G��ƌĂԂ��Ƃ̂ł��鑊�肪���炸�A�͂����đł�����͎t�̓��߂Ƒł������́A���邢��20�Α�̎Ⴂ�����܂łŁA�ӔN�͗͂��������đł��Ȃ���Ȃ�Ȃ������A����Ӗ��s���Ȋ��m�Ƃ�����ł��傤�B
���m�͖{���V�Ƃ��p�����ŏ��̔N�A�P�R�������ɏo�d���܂��B�ŏ��l�i�i�Ƃ��đǂ��R�N�Ԃ̌�����ɏ������܂��B
���m�̐������������߂́A���̔N�̌���őΐ킷�邱�ƂɂȂ�����p�ɑ��āu���m�͔��ɘr���グ���̂ŁA����ł͓����Z�i�i�Ƃ��Čݐ�őł��Ă��炢�����v�Ɛ\������܂��B��p�́A�u�ȑO�ɓ��m�̐�łP�Ǒł��A�����͂������A���̂P�ǂ����Ŏ��͌ݐ�ȂǏ����ł��Ȃ��v�ƒf��܂��B�Ȃ�A�Ə\�Ԍ���Ȃ��Č������邱�ƂɂȂ�A�荇�͓��m���P�i�i�߂Čܒi�i�Ƃ���ݐ�ŁA���̔N�̌�����1�ǂƂ��Ďn�߂��܂����B
�������A���m�͑O���ɐH������ɑ����A�̒���������܂܂ł̑ǂƂȂ�܂����B���Ղł͕K�s�̌`���ł������A����ɐ�p���ɂ��ߓ��m������蔲���A���Ƀ��Z�̖���ŋt�]�P�ڏ������܂����B��p�͕������M����ꂸ�ɂR�x���ׂȂ����Ċm�F�����A�ƌ����Ă��܂��B
���̌�A�Q�ǖړ��m���15�ڏ����A�R�ǖړ��m���ԂR�ڏ����ƂR�A�������Ƃ���Ő�p�͍~�Q���đ������艺���邱�ƂɂȂ�܂����B
���m�����i���ɏ��蓖��Ƃ��Ĉ�l�O�ɂȂ����ƌ������߂́A���̂���Ɍ㌩�������܂��B���̂Ƃ��ɓ��m�͎�������ĂĂ��ꂽ���ɕ邱�Ƃ��瓹�߂𖼐l�ɐ������܂��B���߂́u�t���疼�l�鏊��]�ނȂƖ������Ă���v�Ǝ��ނ��܂����A�u�鏊��]�ނȂƌ������̂ł����āA���l�ɂȂ�ȂƂ͌���Ȃ������v�Ƃ������m�̌��t�ɏ]���A���l�����ׂ��a�����܂��B
���ׂ����l�ƂȂ��Ă���A����ȗ��̗�������̗��K�����蓹�m���ǂ��܂������A�A���ɂ������ĖƏ�̔��s�����߂��č��������ƂɂȂ�܂��B���ł͓������鏊�Ƃ��Č����̖Ə���o���܂������A���݂͌鏊�s�݂̂��߁A���Ƃ܂��͖{���V�Ƃ̈��̖Ə����s���邱�Ƃ��ł��܂���B
�N�����鏊�ɏA���K�v������Ƃ�����A���͂��A�N��l�i���炢���Ă����߂��Ȃ邱�Ƃ����R�ł������A��͂蓹��̈⌾�Ɉ����|���肪�������̂ŁA�܂��і���ɗ���œ��m�̗��������t���Ă��炤�悤�ɗ��݂܂��B���m�́A�剶�̂��铹�߂��鏊�ɏA���ĖƏ�s����̂��ŗǂ̕��@�ł��傤�ƁA����ƈ�邱�Ƃɂ������������܂��B���߂́A�ɂ��Ă̓����҂̈�l�ł��铹�m�����E���Ă����`���Ƃ�A�~���Ɍ鏊�ɏA�C���A�܂��Əs�Ǝ��^�̎葱�����I���Ό鏊�������ɑޔC����Ɩ��āA���悢��鏊�ƂȂ�܂��B
�������A�����ɂ͖Əs������߂͌鏊��ޔC�����A���̌�̌���̍��z���ŏO�̓����ȂǁA�鏊�Ƃ��Ă̐E���𑱂��A�S���Ȃ�܂ł̖�10�N�Ԍ鏊�ł������܂��B
�{���Ȃ瓹��̈⌾�����Ȃ���Γ��߂��鏊�ł��邱�Ƃ͂ނ��듖�R�ł����̂ŁA���m�����߂̑������ɂ͉��������܂���ł������A���߂̖v��P�N�ɂȂ邱��ɂ́A�鏊�ɂ��ĉ��̓������Ȃ����ƌ��ɂ͂��ɓ{��������܂��B
�u���鏊���߂̑������͂��Ƃ����Ⴆ�Ă������������̂ʼn�������Ȃ������B�������A�S���Ȃ��ĂP�N���o�̂Ɏ����ւ̌鏊���E�̖ɂ��ĉ������Ȃ��̂͂Ȃ����B�������̂܂ܕ��u����̂ł���A���ꂩ��̌���͖{�C�őł��Ƃɂ���̂ŁA�����S����B�v
���ۂɂ��̓����̌���œ��m�̑ǂ́A���Ԃ͑S���T�ڏ����B���Ԃ͂P�ɂQ�ڕ����ƂR�ڕ��������݁A�Ƃ��ׂČ��ʂ������Ă��܂����B�k���ɂ��ǂł��邱�Ƃ͖��炩�ŁA���m���u�{�C�őłv�Ƌ�������ɂ͓��m�̂ق��Ŏ��R�Ɏ���������Ă������Ƃ͖��炩�ł��B
���m�ɖ{�C�őł���Ď��͂̍�����R�Ƃ��邱�Ƃ́A���ƂɂƂ��đ�������Ԃ܂��قǂ̖��ł������悤�ł��B�O�Ƃ͍Q�Ăđ��k���A�}���ł��̔N�̂����ɓ��m�i�����l�ɂ����߁A���̗��N���l�鏊�ɐ������܂����B�������A���m�͏j��������Ɍ������āu�t�i���߁j�̂����ŁA10�N�x�ꂽ�v�ƌ����܂����B
�Ő����ɖ{�C�őł����ǂ��c���Ă��炸�A�D�G��s�݂̔߉^�̊��m�ł������A���������ǂ��łǂ���������Ă���̂����킩�点���ɏ��s�E�ڐ����܂Ŏ��R���݂ɑ��삷��Z�|�́A�����̂ق��̊��m�����Ƒ卷�̎��͂ł������Ǝv���܂��B
�܂��A���m�͏����̎��͂����������悤�ł��B
�������勴�@�j�̐Ֆڏ@��Ɠ��m�͌鏫���̈Ⴂ�͂����Ă��N����߂���F������܂����B�������A�@��͐��̏����œ��m�Ƃ͕���Ōܕ��A�����ꖼ�l�ƂȂ�ׂ����̂����̂܂܂ł͋���Ȃ��ƁA���m�ɉ��ǂ��ΐ��ł��܂����B
����Ƃ��A�t�E�@�j�̗��s���ɏ@��͑�������߂ē��m��܂ŏo�|���ĉ��Ԃ��������w���܂����B�������A���������菇�ł��̊Ԃɂ��`�����Ă��܂��܂��B�Ӓn�ɂȂ��ĉ��Ԃ�������^�Œ��݂܂����A�܂��������������Ȃ��܂܋A���ƁA���傤�Ǐ@�j�����s����A��܂��B�����b���āA�u�ǂ�ȏ��������������ׂČ�����v�ƌ�����܂܂Ɏ菇��i�߂�ƁA����ǖʂŎ~�߂����Đ�����@����܂��B�Ȃ�قǂƕG��ł����@��A�����ɖ{���V�ƂɎ���ĕԂ��A���m�ɂ�����ԁI�ƒ��݂܂��B
���̋ǖʂň�ċz�u���A�`���̂P����J��o���ƁA���m�͈ӊO�Ȋ�����Ă��炭�l���A����グ�āu���@�j�a�͗��s����A���܂������H�v�Ɛq�˂܂��B�@��͒m����Łu�����A�܂��A��܂���v�Ɠ����܂����A�����ē��m�u����͂��������B����Ȃ���A���̎�͏@��a�ɂ͎w���Ȃ��B����̎�Ǝv����B�@�j�a������ł͕���ł͂ƂĂ��A�A�A�v�ƔՖʂ�����ďI�ǂ����Ƃ����܂��B�Տ�ŏ@�j�̋A���m�铹�m�́A�܂��������s�����������ł͑��l�҂ł���A�u�Տ�̐��v�ƟӖ�����܂����B
�Z�� �m�� �@�@���̎���́A��E�S�̂����S�Ȑ��ފ��ɂ���܂����B���m�̎���ɍs��ꂽ�k���Ō݂��ɏ������蕉�����肷�����́A�e�ƌ��̋����ӎ��ƌ���S�����킹�A�܂��A���Ƃ̏��i�ɂ͖W�Q����̑��̈������荇���̎���ł����B
���m�́A�鏊�ɏA�C��������A�m����Ֆڂɒ�߂܂��B�m���͓��m�̉��ł������Ƃ����܂��B���m��38�̎Ⴓ�œˑR�S���Ȃ�m����17�ŐՂ��p���܂����A24�̎Ⴓ�ŋ}�����܂��B�݈�7�N�ŁA�ŏI�̒i�ʂ͘Z�i�Ƃ܂�B���ѓI�ɂ͓��Ɍ�����̂�����܂���ł����B
���� �G���@�@�m���̋}���ŁA�Ֆڂ���߂��Ă��Ȃ������{���V�Ƃ̎��̓���́A�ƌ��̍�����c�ɂ��G�����w������܂����B���S�̂̎��͂����ނ��Ă��邱�̎����A�G���͑傫�Ȏ����ɂ܂����܂�܂��B
�܂��A�����E���珘���������������N���܂��B
���̎����A���ނ���������E�ɔ�ׂāA�����E�͎j��ŔN���Ŗ��l�������ƂȂ����ɓ��@�ł�M���ɑ傢�ɐ���オ���Ă��܂����B���̐����ɏ悶�āA�ЂƂ̌Ê��K��j�낤�Ƃ����̂ł��B
���Е�s�����̌�ŏ����w�O���o�d����Ƃ��̐Ȏ��́A��Ɍ������A���Ȃ킿�@�鏊�A�������B����ƌ��C�������ƌ��̏��ł����B����ɁA�鏊���s�݂ɂȂ�Ƃ��͌鏊�̐Ȃɖ{���V�Ɠ��傪�������ƂɂȂ��Ă��܂����B
���l������������̉ƌ��Z�i�̉��ȂƂȂ邱�Ƃɕs�����傫�������Ǝv���܂��B�������́u�鏊����������Ȃɂ����A�e�ƌ��͌鏫�����킸�A�C�̏��v�Ƃ��邱�Ƃ���i���A����́u�ȏ��͎Z���ȗ��̊i���Ƃ��Č��܂��Ă���v�Ɣ��_���܂��B
�K���A��i�̒���Ɏ��Е�s����サ�A���E�i�����d��剪��������s�ƂȂ�Ȏ��͏]���ʂ�ƍ�����������A���Ȃ��܂��B
�Ȏ����������܂������̗��N�A�ܐ��і�������l�鏊��]�݁A�^�����N�����܂��B����������l�̏����l�ł���A�N��I�ɂ��ƌ��l�Ƃ̒��V�i�Ƃ��Ď��M�������Ď��E���܂��B
�����ׂ͓��ӂ������̂́A�G���ƈ����p�͔[�����Ȃ��������߁A����͈�U�͌鏊��������߂܂��B
�������A���x�͏G�������i���ւ̏��i��]�Ƃ��A����ƈ��ׂ��ȑO�̍��݂Ƃ��������Ŕ������܂��B�����ŁA�G���́A�����ɓ�\�Ԍ���肢�o�āA���͂ŏ��i���ʂ������Ƃ��܂��B����͍���ł�����A��\�Ԃ̏�����ɑ̗͓I�ȕs�����������ׂɑ�ł��𗊂݂܂��B
����͔��Ԃ�ł����Ƃ���ŁA�G�����a�ɓ|�ꂽ���ߒ��~����܂��B
�G�����܂��A�Z�i�~�܂�ŖS���Ȃ��Ă��܂��܂��B
���� �����@�@�G�����a�ɓ|��A���̒��O�ɑ��ƌ���ʂ��Ĕ����ɐՂ��p������悤���݂܂����B�����͂P�U�̎Ⴓ�Ŗ{���V���p���܂��B
���̂Ƃ��і���́A�����̌鏊�ɔ�����G�����S���Ȃ������ƂƁA�����̏P�ʂɏ��͂������ƂŁA�@�͏n�����ƍl���A���߂Č鏊�肢���o���܂��B�������A�����͎������{���V�ɏA���Ƃ��ɐ��b�ɂȂ������Ƃ����A�t�ł������G���̎��i���i���ꂽ���Ƃ����ދC�����������A����̌鏊�ɂ��ẮA�����p�ƂƂ��ɑ��ς�炸���̗�����Ƃ�A��s���Ɂu���l�鏊�́A�����ɂ���Č�����ׂ��v�Ɗ肢�o�āA����𗹏����ꂽ���߁A���ɖ���̌鏊�͎������܂���ł����B
���̎���ɂ��A����������m�̗���������܂����A���l�鏊�ƂȂ�ׂ����̂̂��Ȃ������A�ǎ҂̐l�I�ł́A���V�i���i�̈����ׂ������邱�ƂɂȂ�܂����B�����Ă̓���A���m�ɔ�ׂ�Ɩ��炩�ɗ̗͂����̂��A���̈АM�������đł����Q�l�Ɠ����荇�őłƂ��Ƃ������Ƃɖ���������܂����B
���ʂ͈��ׂ̎S�s�ƂȂ�܂����A���ɕ킢�Ə�����߂��A���ׂ͎�����u���{�卑��v�Ə̂������߁A�Ȍ�͗������Ɂu���{�̖��l�͂��̒��x���v�ƌ����т��邱�ƂɂȂ�A���̐旮�����m���������邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�܂����B
�����́A�₩�ȕ\����ɂ��悤�Ȏ������Ȃ��A�d�a�ɜ��A��\���˂łȂ��Ȃ�܂��B
����Ŗ{���V�Ƃ́A�O�㑱���ĂQ�O��Z�i�~�܂�ƂȂ�A�Ղ��p���@���ɑ傫�Ȋ��҂����܂��B
�㐢 �@�� �@�@�O�㑱���ĘZ�i�~�܂�ƒ�����{���V�Ƃ��p�����@���́A����̎g���͖��l�鏊�ɂȂ邱�ƂƁA���ނ���������E���Ăѐ���グ�邱�Ƃƍl���܂����B���̂��߂ɂ́A�ƌ��Ԃ̋����ӎ��������A�ϋɓI�ɑǂ���p���������āA�����̏��i�̂��߂ɖҗ�ȉ^����W�J���܂��B
�܂��A���i�ւ̏��i��]�Ƃ��́A�ŏ��u�{���V�Ƃ͎O�㑱���ĕs�K�����ł���A�i�ʂ���������Z�i�ɂƂǂ܂��Ă���B���i�ɓ��ӂ��Ă��炦�Ȃ����B�v�Ɖƌ���c�Ɏ��������܂��B
�������A���Ƃ̐Ֆڏt�B��щƂ̐V����������ܒi����Z�i�ɏ��i�����ė~�����Ȃǂƌ����������o����܂��B
�@���ɂ��Ă݂�A����Ȃǂ͑卷�ŏ����z���Ă���A�t�B�͎����Ƃ̑Ǔ����Ă���̂ŁA�ꏏ�ɂ���Ă͂��Ȃ�Ȃ��Ƌt�ɒf��܂��B
��Ȃ����Ď@���̏��i��F�߂Ȃ����ׂɁA���ɑ����\�����ނ����Ȃ��Ɣ���A�悤�₭���i�֏��i��F�߂����܂��B
���i���i��́A�����Ȑ��тɂ���ĂV�N��ɁA���ׂƂƂ��ɔ��i�����l�ɏ��i���܂��B���̂Ƃ����A���ׂ͎������ÎQ�ł��邱�Ƃ��|�ɂƂ��āA�������i�������������Ȃ��ӂ��ł��������A�@�����u���͏��ł͉������͂Ȃ��v�Ɖ������Ă��܂��܂��B
�����l�ƂȂ��Ă���͂��P�N�����āA�@���͔O��ł��������l�鏊��]�݂܂��B����́A�������Ɏ��������Ƃ��āA���ƑS�Ăɔ�����܂��B���͔͂F�߂�A�������܂��Ⴂ�A�Ƃ������̗��R�ɑ��āA�u�҂���͂Ȃ��B����ȏ㔽����Ȃ瑈����肢�o��v�Ƃ����@���B
���c�͌��A���ׂ�ɑ����\�Ԃ��s���邱�ƂɂȂ�܂��B���ׂ́A��̏G���ɑ����āA���g�Q�x�ڂ̑���ƂȂ�܂��B
�@���́A�[����T�A�����A������ԏ����đł����ނ��Ƃ��ł���Ώ����錾���������ł������A���ׂ͎��̈�Ԃ������Ɨ��R�����đłƂ��Ƃ��܂���B�Ƃ��ς₵���@���͈��ׂɕ�����F�߂�悤�ɓ`���܂����A���ׂ́u�܂��Z�ԕ����z���đł����܂ꂽ�킯�ł͂Ȃ��v�Ɖ����܂��B�@���͂���Ɂu�Â�����l�A�������ꍇ�͑ł����݂ƂȂ����Ⴊ����v�ƒNj����܂����A�u�Ȃ�ǂ����Ďl�A���̎��_�ł�������Ȃ������̂��B�܋ǖڂ�ł����̂͘Z�Ԏ蒼������m�����̂ł͂Ȃ����v�ƁA���ׂɂ��ꂱ��Ɠ�Ȃ������܂��B
�������A���ǂ͈��ׂ������Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���A�Ō�̈�Ԃ�ł��Ȃ��܂����錾���F�߂��āA�@���͖��l�ʂɏ���܂����B�A���A�͂ɑi��������������߂������߂ɁA�鏊�ւ̏A�C�͖�R�N�̒������Ԃ�u������ɂȂ�܂����B
���m�ȗ��̌鏊�̒a���ɁA��E�͍Ăъ��C�����߂����������ƂȂ����_�Ŏ@���́u��E�����̑c�v�Ƃ��ĕ]������܂����A���ۂɑ��Ƃ����|�I�ɑł������͂͂����ƌ��������ׂ����Ƃ�����������܂��B
�@���́A�鏊�A�C��{���V��c�ɕ�Q���ĕ��邽�߁A�]�˂��狞�s������܂œ��C����喼�s����݂̍������Ȃ��čs���A���̂Ƃ��{���V�Ƃ̍��Y�̑唼���g���ʂ����Ă��܂����Ƃ����܂��B
�\�� �� �@�@�@���ɂ���Č�E�͊��C�����߂�����́A�{���V�̐Ղ��p�����Ƃ��̓�����̈����m�A�O�Ɓi�ƌ��ƈ��ʓ��̊W�̂���n��j����͖쌳�ՁA�������i�ȂǁA��������₩�Ȑ킢�̊����������m�������A�e�Ƃ��Ƃɂ��ۛ��A�㉇�҂̌�������ȂǁA�ǂ̋@����ɑ����Ȃ�܂����B
�́A����̑ǐ����j��ő���46�ǂ���A���N�u���D�݁v�i���K�̌���̌�ɁA�����P�ǎw���ɂ��ǂ�g�܂��j���s��ꂽ���Ƃ�����A���̂ق����M�S�Ȉ��D�҂������Ȃ��Ă����Ǝv���܂��B
�@������܂ł̂��悻30�N�Ԃ̂����ɁA�S����240�N��500�ǂ̂�����120�ǂ��ł��ꂽ�قǂ̐���Ȏ���ł����B
�́A59�ŏd�a�ɜ��A�Ɠ�����ɏ����ĉB�����悤�ƍl���܂����B�������A�@���E�ƂQ�㑱���Ė{���V�Ƃ̊i���������邽�߂̏o������A���ォ����炦��\�͂��ׂĂ�����Ă����Ƃ����ԓx�������̂ŁA�u�\�͌���ɓn�����A�B���������肽���v�Ɛ\���o���̂ł��B
���̑ԓx��ᒂɏ�������A�̉B�����Ȃ��Ȃ��F�߂�ꂸ�A���ۂɉB���̎葱�����s����܂ŁA�T�����ԗ̕a������������Ƃ������Ƃ�����܂����B
���̔������A��̌���͔��Ȍ���Ƃł������Ƃ����܂��B
�\�ꐢ ���� �@�@�̐Ղ��p��������́A���̖��l�ɂ����Ȃ����͎҂ł����B�������A�܂������̓�����ɁA����Ƌ��ɖ��l���ƕ��я̂�������m���i��m�j�����܂����B�������コ���قȂ�A�ǂ�������R���l�ɂȂ��Ă����������Ȃ����͂������Ă��܂������A�Q�l�͍D�G��Ƃ��ĂW�O�Ԉȏ�킢�܂������̌݊p�̐��т��c���܂����B���̓��e���㐢���猩�āu����̌�������Ȃ����ǁv�ɂ��ӂ�Ă��܂��B
�݂��ɐl�i���D��Ă������߁A�u���l�͈ꎞ�㒆�ɔ�����o�����l�҂��A���R�ɐ����������̂łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ̍l������A�ǂ�������l�ɂȂ낤�Ƃ����ӗ~�������邱�Ƃ�����܂���ł����B
���l�ɂȂ�Ȃ������s�^�����A�I���D�G��ƌĂ�ē�������������ƂŐ��X�̖��ǂ��c�����Ƃ��ł������Ƃ�����Ƃł��傤�B
����̉₩�ŗ͋��������ƁA�m���̏a���n���d����������̂Ԃ��荇���́A�D�ΏƂ������Ȃ��瑽���̖��ǁA�D�ǂ��Y�݂܂����B
����́A�{���V�Ɠ�����Q�O�N�߂���A�Ɠ���������Ə�a�ɏ���B�����܂��B���������y���݂ɁA��E�Ƃ̊ւ�肠������؎����܂���ł����B
��ɏq�ׂ�悤�ɁA��a�͖��l�鏊�ƂȂ邽�߂ɍ������߂��点�A�m������������ł����܂��B�m���ƏI���̃��C�o���ł���������ł����A��q�̏�a�Ƃ̑����ɉ�����o���������A��a�̎��R�ɂ�点���悤�ł��B
��a���O��̖��l�ɏA�������Ƃ����͂������N�A��������܂����B
�\�� ��a �@�@�]�ˎ���ɂ͊����ƌĂ��҂��Q�l���܂����B�O���ƌ����铹��ɑ��āA��a�͌㐹�ƌ����܂����B�������A��a�̎��͂͂Ƃ������A���l�鏊�����������A�d���m����悤�ɂȂ�ƁA�㐹�̖��͌�ɂȂ��Ă���l�i�����Ől�C�̂������G��Ɏ���ĕς���Ă��܂��܂��B
��a�̊����͗͐�Ƃł���A������̂ɂ킩��₷�����łG��ɐl�C���ڂ����ʂ�����܂����A�u��͐킢�ł���v��n�ōs����a�͂����ƌ��������ׂ��ł���ƕ]������v�����m���������܂��B
��a�͔Ӑ��^�̊��m�ł���A����剺�ɂ͏�a��1�Ώ�ɉ��ђq��Ƃ����V�ˌ^�̊��m������A����̐Ֆڂ͒q��ƂȂ邱�Ƃ��قƂ�nj��܂��Ă��܂����B�������A�ՖڂɎw�����钼�O�q��͕a�Ŗv���A��a�ɐՖڂ��܂���Ă��邱�ƂɂȂ�܂����B
29�ł悤�₭�ܒi�A32�ŐՖڂƂȂ�Ɠ����ɘZ�i�ɐi�݂悤�₭�˔\���J�Ԃ��܂��B
��a�̃��C�o���Ƃ����ƁA������ɖ��l�̒n�ʂ�_���Ă��������ׁi�����j�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B�������A�Q�l�̑ǂ͏�a��36�A�܂��Ֆڂ̂����̑ǂ��Ō�Ƃ��āA����Ȍ�͂܂������s���Ă��܂���B11�ΔN���̈��ׂ̎��͂�����ɏ[������ɂ�A��a�̖��l�ւ̍ő�̏�Q�ƂȂ邱�Ƃ��킩��������ł��傤�B
��a41�̔N���A����͏�a�����i�ɐi�߁A���̔N�̂����ɉB���͂����o���Ė{���V�Ƃ̉Ɠ�����܂��B�܂��A���N�̐����ɂ͂����ɔ��i�����l�ɂ����ނ��ƂɂȂ�܂����A��a�͂��Ƃ��ƒi�ʂ�Ⴍ�}�����A���͓I�ɂ͉����肪�Ȃ������̂ŁA���Ƃ̈٘_�����ޗ]�n������܂���ł����B����ɁA�����̏��i�ɐ旧���āA�������O�ɗь����ƈ����ׂ����i�ɐ��E���Ă����̂ŁA����������������܂��悤�Ȃ��Ƃ͂���܂���ł����B
��a�����i�ւ̏��i���ʂ����ƁA���̂܂܂ł͏�a����ɖ��l�ƂȂ鋰�ꂪ����ƍl�������ׂ́A�����ɂ���Ď��������i�ɏ��A�ǂ������Ƃ��܂��B
�܂��A���ׂ͎����������i��ʂ��ď�a�ɘb�����������܂��B�u��a�a�͖���{���V�Ƃ̓��̂Ŕ��i�A�N������̏������Ƃ���ł�����A�����ꖼ�l�鏊��_���ł��傤�B�ь����͂��Ƃ��Ɠ���Ȃ̂Ŗ��Ȃ��B����������Ƃً͈c��������ł��傤�B���̋ύt���Ȃ�Ƃ�����͈̂��Ƃ̋��O���B�M���̒n�ʂ̑��ł߂Ƃ��āA���ׂ̋��͂����t���邽�߂ɔ��i�ɂ����߂Ăق����B�v
��a�́A��m�i�m���j�̏o�����킩��Ȃ������̂ł����A���Ƃ�G�ɂ܂킷���͗ǂ��ƍl���āA�����܂��ɏ������܂����B
���i�́A���ɐ�m��K�˂Ĉ��ׂ̔��i���i�̓��ӂ����߂܂��B�������A��m�́u���i�ɏ���Ă܂��������A���̊Ԏ荇�炵���荇�͂P�ǂ��ł��Ă��Ȃ��̂ŁA�ƂĂ��^�������˂�v�ƕԓ����܂��B
���i�́A�u�������Ǝv�����̂ő���̊肢����p�ӂ��Ă���܂��B���������������āA��s���ɒ�o���܂��傤�v�Ƃ��������܂����A���ꂪ����ɐ�m�̋t�ɐG��A������������邱�ƂɂȂ�܂��B
��a�́A��m�ƈ��ׂ������ł��ċ��|��ɂȂ�悢�Ǝv���܂������A���ׂ̎v�f��T���Ă݂�ƁA���ׂ͐�m�Ƒ����ł��Ƃŕ������A�V��Ȑ�m�������ł���O�ɑ̂��Q���Ă��܂��A�ō��ʁA�Œ��V�̐�m�Ƃ�����ő��������тŖ��l�鏊��]�����Ƃ������̂ł����B
�����ŁA��a�͐�m�ƈ��ׂ̑����肢�������A�ь�����Y��l�Ƃ��āA���l�鏊�A�C�肢���o���Ă��܂��܂��B
��m�͓ˑR�̓W�J�ɋ����܂����A�@������ɕq�ł��������ׂ͐�m�ɑ��k�����������܂��B�u��a�̖��l��j�~����ɂ͑��邵������܂���B���A�i�ʂőR�ł���̂͐�m�搶�̂݁B���͂ł͂܂��܂������Ȃ��ł��傤���A���������ɂȂ�ΎႢ��a�̗̑͂ɂ���Ă��܂���������܂���B�����ŁA�����������ė����ď�a�̖��l���~�߂����Ǝv���܂��B�����A�R���邽�߂ɂ́A���i�ł͋�������B�Γ��̔��i�ɏ��i�����Ă��炦�܂��B�v
�������āA��m�����܂��b�ɏ悹�����ׂ́A���i�Ƃ��ĂقƂ�Ǒǂ������ɔ��i�ɏ��i���܂��B
���悢���a���鏊�A�C�肢�ɂ��Č�ŏO�̉���s���܂��B���V�i�̐�m���A��ŏO�S���ɏ�a�̌鏊�ɂ��Ă̈ӌ������߁A���S�ł͈��ׂ��ًc��������̂�҂��Ă��܂����B���������ׂ͉������킸�ɂ������߁A����������m�́u�����͏�a�̖��l�鏊�ɏ��������˂�B�]�ނȂ玩���Ə�����ł悤�Ɂv�Ɛ錾���܂��B
���ׂ̑_���́A��a�Ɛ�m���g����鑈���Ŕ�ꂽ�Ƃ���ŁA���҂ɏ����݁A���v�̗��邱�Ƃł����B���Е�s����A��m�Ə�a�̏������ق����鏊�ɂȂ邱�ƂɈˑ��͂Ȃ����Ɩ���A���ׂ͏����c�����ق��Ǝ荇��]�ނƐ\���o�܂����B
�������A��m�Ə�a�̑ǂ́A���悻�P�N�ԑǓ��������܂炸�ɂ��܂����B�����ŏ�a�͈��ׂɍ����̎莆�𑗂�܂��B
�u���̂܂܂̏�Ԃł́A����m������̂悤�ɂǂ�������l�ɂȂꂸ�ɏI���B��E����̂��߂ɂ��鏊�̒����s�݂�����悤�ł͂Ȃ����B�܂��A�N���ł��鎩�������l�ƂȂ�鏊�ɏA�C���A�U�N��Ɉ��דa�ɏ���Ƃ����b�͂ǂ����낤���B�����Ƃ��ẮA�����̖��l�𐄑E����ꕶ���������ƁA���l�鏊������Ƃ��Ɉ��דa�������S���������o�����ƁB���s�̂��߂Ɍ݂��Ɏ��q��l���Ƃ��ėa���邱�ƁB�v
���ׂ́A��S���̎x�o�͒ɂ����A�U�N�҂��Ƃ͎����ɂƂ��ĕs���ȏ����ł͂��邪�A�P�P�̔N��͂��邵�A�U�N�ڈȍ~�͎����������Ɩ��l�ł�����ƍl���A��a�̐\���o���܂��B
���ʂɂ����ׂ̐��E���Y���Ė��l�鏊���肢�o����A��a�͈��ׂƂ̐l�������̖����܂��B��a���x���ꂽ�ƋC�Â������ׂ́A���߂ď����݂܂������E������������Ƃ����a�Ɏ�荇���Ă��炦�܂���B���ׂ́u���E��͏��������A���̌㎩���͘r�������A������ׂ���͂������B�v�Ƌꂵ������������܂��B
��s���͒��V��m���Ă�ő��k���܂��B�u�Q�l�Ƃ��r�͏\���Ƃ����Ă���̂�����A�����ł����Č��߂���悢�ł��傤�v�ƁA�Q�l�ɂ����₩�Ȏd�Ԃ������܂����B
��a�́A�����������l�ɂȂ�Ǝv�����Ƃ���A�܂��扄���ɂ���A���������ׂƑ����ł��ƂɂȂ�͕̂��̋�J�ł͂Ȃ��A�ƌ����ɑ��k���܂��B
����ƁA�����́u�����͐��˔˂̏o�g�ŁA�˂ɂ͑����炪�����܂��B�B�������ɗ���ŁA�����������Ă��炢�܂��傤�B���̑���A���l�ƂȂ����Ƃ��͎����i�ɏ��i�����Ăق����v�Ɩ��A��a�𑈌��ł��ƂȂ��A���l�鏊�ɏA�C���܂��B
��a�����l�ƂȂ��Ă�����A���ׂ͂��܂��ꂽ������������A�Ȃ�Ƃ���a���������艺�낷�@���_���Ă��܂����B�����ň��ׂ���v���Ă����̂��A��D���̑喼�����āA�e�ƌ��������ő傫�Ȍ����J�Â��Ă��炢�A���̐ȏ�Ő��Ԃ̒��ڂ���g�ݍ��킹�Ƃ��ď�a�Ƃ̑ǂ�g��ł��炤���Ƃł����B���ꂪ���������̂��A���O�f���̋ǂƂ��ėL���ȑǂ��g�܂ꂽ�u�����Ƃ̌��v�ł��B
���ׂ͏����Ƃ̑����O�ɂ��āA��Ԓ�q�̐Ԑ����O�Ɨ��K�ǂ����܂����A���O�̐��������������ׂ����������đ��������悤�ɂȂ��Ă��܂����B
�����ň��ׂ́A���x�̌��ŏ�a�ɓ�����͎̂����ł͂Ȃ����O�ɂ��悤�ƍl���܂��B�����炭��a����킷��ɈႢ�Ȃ��B���i�̎�����莵�i�̈��O�ɔs���u���i�̐�Ɋ��s����Ƃ͖��l�̎��i�������v�Ƙb�������čs���₷���B
�������āA�����̌��ł͏�a�Ɉ��O��������A���Ղ͈��Ɣ�`�̑�̊��ɂ���a����킷�邪�A���ՂɂȂ��āu��a�̎O����v�Ƃ�����D��ŋt�]�B���O�͎t�̗��݂��ʂ������߂ɓ�ǑŊJ�����葱���A���ɂ�������Ȃ�ʖ��O������Տ�ɓf�����ē|��A���𗎂Ƃ��܂��B
���ׂ�ނ������̂́A���N���ď�a�ɂ����ЂƂ̖�肪�����オ��܂��B���������l�鏊�ƂȂ����猳���i�ɏ��点��Ƃ��������s���Ȃ��������߂ɁA�����͌��������������˔˂ɖʖڂ��������̂ł��B�����͌�ŏO�Ƃ͂������Ƃ̏o�ł���A���m�Ƃ��Ă̒p���������ׂ��A��a�ɑ����\�����ގ��ԂƂȂ�܂��B��a�͖��������ߍ��݂܂����A�������疽�ɑウ�Ă��Ƒ����\�����܂ꂽ��A���Ƃ��Ƃ̋����Ȗ��l�A�C���e�����āA���������Ɍ鏊�B�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ɒǂ����܂�邱�ƂɂȂ�̂ł����B
�\�O�� ��� �@�@���́A�\�ꐢ����̎��q�ł��B�\��a�͗��̖{���V�Ƃ̒��ł��Ӑ��^�ł���A�Ֆڌ��ł���Ȃ��瑁���������ђq��̌�A�����̒�q�̒����玩�������o���Ă��ꂽ����ɉ��������Ă��܂����B
����̂ɁA���Ɏ����̌���p�����A���̌�ɏG�a��ՖڂƂ��Đ������̂́A�{���V�ƂƂ��Ă̌��ƁA���Ԃ��̎��𗼗��������őP��ł������Ƃ����܂��B
���́A�����̌�E�Ől�i�҂Ƃ��Ēm���Ă��܂������A�i�ʂ͘Z�i���x�A�{���V�Ɠ���Ƃ��Ă���Ŏ��i�ɏグ��ꂽ�Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B
��a���B���������ƁA���ׂ����l�鏊���肢�o�邱�Ƃ͗\�z����Ă��܂������A���̂Ƃ��ɔ����đ���Ɏ������ނ̂�����ł��鎩���ł͂Ȃ��A�ՖځA�����Z�݂̏G�a�Ă悤�Ƃ����Ƃ���A�G�a�̎��͂�m��A���������������ׂɁu���R���傪�o��ׂ��v�Ɣ��_����A���̏d�ӂ��炩�a�C�Ə̂��Ĉ����������Ă��܂��܂����B��A�G�a�ɑS�Ă�������ނ��܂��B
�\�l�� �G�a �@�@�G�a�́A���ׂ̖��l�肢��j�~���A�����̂��킽�����������Ɍ�E���ێ����A�����ɂȂ��Ă���͌�ŏO�̐����c��̂��߂ɖz�����Ȃ���Ȃ�܂���ł����B���̂��߂ɁA�\���ȗ͗ʂ�����Ȃ��疼�l�ƂȂ�ׂ��������킵�Ă��܂��܂��B���l�ɔ䌨����͗ʂ������Ȃ���A���l�ƂȂ�ׂ����Ȃ������A����E�m���E�������ׁE�G�a�́A��N�w�͌�l�N�x�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B
��a�̉B����A���ׂ͒����ɖ��l�肢���o�A�N����l���w�����Ĉ��ׂƑ����ł�����悤�������A�G�a���Q�����ԂɂS�ǂ̑ǂ��������܂��B
���̑����P�ǂ͏G�a�̊����B���ׂ͏G�a�̐����ɋ����A�܂����g������ɂ��̗͂̐����������܂��B���̂܂ܑ���𑱂��邱�Ƃ͓���ł͂Ȃ��Ǝv�������ׂ́A�a�C�𗝗R�ɂ�������͌鏊�肢����艺���A����𒆎~���܂��B
���̂Q�N��A���ׂ͑̒������Ăь鏊��_���܂��B�������A�O�������艺�����肢���ȒP�ɍēx�o���킯�ɂ����܂���B�e���̂�����{�ɗ���Ō����Â��Ă��炢�A�����ōĂяG�a�Ƒǂ��܂��B
�G�a�Ƃ��Ă��A�������̌����ƁA���ׂ��Ăі��l�A�C��\���o�邱�Ƃ�\�����đǂɗՂ݂܂��B
���̌�͈��ׂ��G�a�ɔ��������Ă̖��ǂł������A�P�ڋy�Ȃ��Ɠǂ��ׂ������������A�G�a�͂����ǂ������ŏ��������߁A�Q�x�ڂ̈��ז��l�肢��j�~���܂��B
�����āA�����N�̌���ň��ׂƏG�a�͂R�x�ڂ̏������s���܂��B���ׂ͍ŋ߂V�N������߂Ă��܂���ł������A�˔@���A���A���K�̑ǂŎZ�m�Ƒł�����A���D�݂ŏG�a�Ƃ̑ǂ�]�݂܂����B
�������A���̌���G�a�̊����ɏI���A���ɏG�a�́A�R�x���ׂ̖��l�肢���A���Ƃ��Ƃ��j�~�����̂ł����B
���l�ƂȂ鎞�Ȃ��������ׂ́A�ӔN�{���V�ƂƘa�����A�Ռp���̂��Ȃ����Ƃ̂��߂ɁA��a�̎��q��{�q�ɂ��炢�����Ď����̐Ռp���Ƃ��܂����B
���ׁi�����j���v���A�G�a�͂��悢�於�l�鏊���肢�o�܂��B�������A���̂Ƃ��̘V�������Ƃ̋���ł��������߁A���_��扄������A���ɋp������܂��B
���̔N�A�G�a�͌���ŏ\�l�����ׁi���{���ׁA�����̓���j�Ƒǂ��邱�ƂɂȂ�A���Ƃ̔��𒾖ق������D�̋@��܂����B����܂ł̎��т���l����ΏG�a�����ł�������ȂǍl�����Ȃ�����ł������A���̂P�ǂɌ����āu�������G�a�̖��l��j�~����Ə��ڂ����̂ł͂Ȃ����v�ƌ�����قǂɈ��ׂ̏o�����ǂ��A���ɂP�ڋy���A�G�a�̖��l�͎������܂���ł����B
�ȍ~�́A�����̐���s����Ȏ����ɓ���A�R�����̗��s�ŐՖڏG���S�����A��������~�ƂȂ�܂��B
�G����������Ɏ�͑傫���������A���̌�ɂ͏G�Ⴊ���܂����B�G��̐����͒������A����Ŗ{���V�Ƃ����ׂ��Ǝv�������A��a�̌�Ȃ̌��o���ɂ����A�G��͖{���V�Ƃ��łĂ��܂��܂��B
�L�]�Ȍ�p�҂������A�G�a�͖{���V�Ƃ̐ՖڂɎ��q�̏G�x�����Ă܂��B
�����ېV��A���{�̘\�����������@�l�Ƃ́A�₩�ɋ��R��ԂƂȂ�A�{���V�Ƃ��o���Ď��͐��\�˂��ޏāB���ӂ̏G�a�͖����U�N�ɖv���܂����B
�Ֆ� �G�� �@�@�G�a�̐ՖڂƂȂ�Ȃ���A34�ŕa�����{���V���p�����Ƃ��ł��Ȃ������ɂ��ւ�炸�A�G��͗��{���V�̒��ōł������Ȋ��m�ƌ�����ł��傤�B
�c�������Ɋւ����b�������A�����Ă����^��������~�Ƃ��A�ܟB�ʼn�����ɕ����߂��璆�ɂ������ՐŊ�������ׂĂ����Ƃ����悤�Șb���`����Ă��܂����A���̓V�˂͎����ł������炵���c�����Ĕ˂̗L�͎҂̌�돂�Ė{���V�Ƃɓ���B�B�����Ă�����a�Ɠ���̂R�q�ǂ�ł��܂��B���̌�͑ł������ƂȂ�܂������A��a�͏G��̍˔\�����āu���ꂼ150�N���̓V�ˁB�V��̐����͑傢�ɑ������낤�v�ƌ�����Ƃ����܂��B150�N���Ƃ����̂́A����ȗ����Ƃ����ő勉�̎^���ł����B
���҂̒ʂ萬�������G��́A�G�a������ɏA��������ɐՖڂƂȂ�A���悢�����ւ̏o�d���ʂ����܂��B
�G��́A13�N�Ԃ�19�ǂ̌����ł��A�S������Ƃ��������𐬂����������Ƃ͗ǂ��m���Ă��܂��B�A���A�r���щƐՖڔ��h�Ƃ̂R�q�ǂ��g�܂ꂻ���ɂȂ����Ƃ��́A���h���щƂ��p���ł���ɂ������ƒf��ȂǁA�{�l���S�����ӎ����Ēu���������t�V������܂��B
�����G���p�������ԂŌ����ȏ�����ڎw���z�͏G�����ƌĂ�A�����ɂ�������܂������A�]�˂̑�ƃR�����̗��s�ɂ���Č���͒��f�A����ɐ����S�����A���]����킷���̂��Ƃ��R�������҂̊ŕa�ɂ�����A���g���������Ė��𗎂Ƃ����ƂɂȂ����̂ł����B
�\�ܐ� �G�x�@�@�G�a�́A�ՖڏG�S���Ȃ������Ƃ�傢�ɔ߂��݂܂����A���̂�����ɏG�Ⴊ�����������������Ă��܂����̂ŁA���߂ďG���ՖڂƂ��悤�ƌ��߂Ă��܂����B
�������A��a�̖��S�l�ŏG��̋`��ł����鐨�q���G��������Ă���A�G�a�͏G��Ֆڂ�������߂���Ȃ��Ȃ�܂����B
�����āA�Ֆڂɕt�����̂́A�G�a�̒��j�łP�S�ΎO�i�̏G�x�ł����B�G�x�́A����{���V�Ƃ̑����̂��߂ɐ��i���Â��܂������A�\�ܐ����p���ł���5�N�A���ɏd���ɑς��ꂸ�ɐ��_�Ɉُ���������A�މB������Ȃ��Ȃ�܂����B
�\�Z�� �G�� �@�@�G�x���}�ɉB�����邱�ƂɂȂ�A�G�a�̎��j�ŗщƗ{�q�ƂȂ��Ă����G�h�ƁA�O�j�̕S�O�Y�i�G���j���b�����������ʁA���̖{���V�͏G�Ⴕ�����Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂����B
�����ŁA�V��̒��ŏ�a�̎O�j�ł��钆��T�O�Y��ʂ��ďG��ɏP�ʂ�Őf����悤�ɗ��݂܂����A�T�O�Y�́A�u�܂��G�x�����Ȃ��Ƃ͌���Ȃ��B�������̂��Ƃ�����ΕS�O�Y�Ɍp������悢�v�ƌ����ė������܂���ł����B
�G�h�́A�S�O�Y�����ĂĐՖڂƂ��邱�ƂɌ��߂܂������A����𐄑E�����T�O�Y���A���́A������������{���V�̐Ղ��p����S�������ďG��ɘb�������čs�����ƕ��������߂ɕ��S���܂��B
�T�O�Y�͑O����|���āA�G���Ֆڂɂ��悤�ƌ���������܂����A���ꂪ���������G�h��{�点�܂��B
�G��́A���͂ɐU���Č��ǂ͖{���V�Ƃ����邱�ƂɂȂ�A�S�O�Y���G���𖼏��\�Z�����p���܂��B�������A�G���͌Z��̂Ȃ��ł����Ƃ��˔\�Ɍb�܂ꂸ�A�{���V�ƂȂ����Ƃ��͎O�i�ł����B
���ɂ����Ă��A���Ƃ̍��i�҂Ɂu���������Ă���A�����~�𗊂ށv�Ɨp�������������āA����S���Ă��u����A�̂���̕Ȃ��ł��������v�ȂǂƂ��������n���ł����B
�l�i����オ�邱�Ƃ��Ȃ������G���ɂ́A�{���V�Ɠ���̐Ȃ͑����̏d���ł������ł��傤�B��i�̖{���V�������˂��G�h�́A�щƂ�f�₳���Ė{���V�Ƃɖ߂�A��̏G�������I�ɉB�������āA�������\�������p�����ƂɂȂ�܂��B
�G���́A�����ɖ{���V�ɐ�����ꂽ���Ǝv���ƁA�}�ɔ��D���ꂽ�悤�ŁA�Z�̏G�h�̐g����ɓ{��A�Z��͂����ƕs���ł������Ƃ����܂��B
�\���� �G�h �@�@�G�a�̂R�l�̑��q�����܂����B�c������A�R�l������őǂ��Ă���̂����Ō��Ă����G�a�ɁA����l���₢�����܂����B�u�R�l�̑��q�̒��ŒN����ԍ˔\������܂����H�v����ƁA�G�a�͖ق��Ď��j�̏G�h���w�������Ƃ����܂��B
�������A�{���V�Ƃɂ́A�G�a�̂X�Ή��̐ՖڏG��A����ɂ����X�Ή��ɂ͖�g�i�G��j�����āA��������Ǝv��ꂽ���߁A�G�h��Ռp���̂��Ȃ��щƂɗ{�q�ɏo���A�щƏ\�O�����p�����܂����B
�{���V�G�x�̎���ɁA�G�Ⴊ�͌�̌�������s���g�D�ł���u���~�Ёv��ݗ��B������Ƃ������i������@�l�Ƃ����Q�W�Ȃ��A����ɎQ�����܂����B
���~�ЎQ���Ǝ����������āA�G�x�̐��_�a�ɂ��A�{���V���̕K�v�������܂������A�G�h���l�����̂́A�����Ŏ������{���V�Ƃɖ߂�ƗщƂ͒f��A�ƌ��̌����ɂ���Đ��͂���܂���~�ЂɈ��ݍ��܂ꂩ�˂Ȃ��Ƃ��āA��̏G���Ɍp�����邱�Ƃł����B
�������A���͎O�i�̖{���V�͑��ƌ�����y���A�G���{�l���㏸�u�����Ȃ��A�G�h�ɑ��Ă͖����ɖ{���V�ɏA�����ꂽ���݂������Ă��܂����B
�G�h�́A�������̉^�����������A�]�ˎ��ォ��̏���ɏ]���A���~�Ђł̐Ȏ����{���V���ŏ�ȂƂ�������A�i�ʂ̔��s�͉ƌ��̓Ɛ�Ƃ��A���~�Ђɂ͔F�߂Ȃ��Ȃǂ�O�ꂵ�܂����B
�G����͂��ߕ��~�Ђ̊���������ɂ��ƂȂ����]�����̂́A�ƌ��̋��R��Ԃɔ�ׁA���~�Ђ͌㉇�҂����������I�ɂЂ��傤�ɖL���ł��������߁A�����̂ĂĂ��������������ł��B
�������A���~�Ђ̎荇�ɂ����Ēi�ʐ��A���i�����\���Ȃ����Ƃ͎��ۂɕ��Q�������A��ɕ��~�Ђ͖Əs�ɓ��ݐ�܂��B��������~�ЂƉƌ��Ԃ̒������ƂȂ�܂����B
�������A���~�Ђ������̌㉇�҂Ĕ��W����ɂ�A���̉^�c�����̊��p�̈���G�Ⴊ���d�邱�ƂȂǂɕs��������A���҂͕��܂��B
�����ɕ��Ă݂�ƁA�{���V�Ƃ̋��R���͂��߁A�e�ƌ��̑��S�̊�@������܂��B�܂��A�щƂł͐�㔐�h�̖��S�l�������̈���������Ă���A���Y���g���ʂ����Ă��܂������߁A�G�h�͗щƂ̒f������f���Ė{���V�Ƃɖ߂�A�G�������I�Ɏ�B�������ď\�������p���܂��B
�{���V�Ƃ��p�����Ƃ����Ă��A���ɕ����̎�i���Ȃ��G�h�ɁA�����ېV�̉e�̎��͎҂ł������㓡�ێ��Y�́A�{���V���ċ���������ڎw���Ȃ�A���͂ɂ����Ď��̑��l�҂Ɉς˂�̂��őP�ł���Ɛ������܂��B����Ɉ��B�A���ʋς�̐����ɂ���āA�T�N�Ԃ�ɕ��~�Ђ̎荇�ɎQ�����A�G��Ƙa�����đǂ��邱�ƂɂȂ�܂����B
���ꂩ��A���~�Ђ̒���ŘA�����đǁi�ŏI�I��10�ԑ�����ꂽ�̂ŁA��Ɂu�a���̏\�Ԍ�v�ȂǂƂ����܂��j�B8�ǂ߂�ł������ƁA�G�h�͂������Ԃ������āA�{���V�̍����A���͑��ʂł�G��ɏ��邱�Ƃ�^���Ɍ������܂��B
�G�h�G��̑ǂ͂W�ǖڂ܂ŏG��̂T���R�s�B���̂܂G�h���A�s����Ǝ荇����ƂȂ��Ă��܂��S�z������܂����B�荇���ꂽ�����ɖ{���V���ړ�����ƁA���������͂ŒD��ꂽ���̂悤�Ȉ�ۂ�^�����˂܂���B�G�h�K���ɑ�X�ǂ������A�Ȃ�Ƃ��ł����݂�܂��B
�G�h�́A���ɖ{���V�̑T�������ӂ��܂����A�{���V�Ƃ̑����ƌ��Ђ̈ێ������߂ď��������܂��B
�P�A�ƌ����c�ɂ��i�ʐ��x���A���~�ЂɓK�p���邱��
�Q�A���~�Ђ̔��s����i�ʖƏ�ɁA�{���V�̏�����K�v�Ƃ��邱��
�R�A�G��̌�A�{���V�p���҂́A�����₵����݂Ȃ��A���͂ɂ����Č��肷�邱��
�܂��A���̂R���ȊO�ɂ��A�{���V����͕��~�ЎВ������C���邱�Ƃ���A�{���V�Ƃ̑������G��ɑ������ƂɂȂ�܂����B
�G�h�͂܂��A�G��̕��~�Вi�ʂł��锪�i��{���V�̖��Ő����ɔF�߁A���̂����Ŗ{���V������܂��B��������G��͒����ɏG�h�����i�ɂ����߂܂����B
�������āA��P�O�ǂ��ł���܂����A�݂��̏P�ʂƏ��i�̗�������ɔ�I����`�ƂȂ�܂����B
�������A�G�Ⴊ�{���V�Ƃ��đǂ�����͂��̂P�ǂ݂̂ŁA�P����I�Ȃǂ̉���Â��Ԃ��Ȃ��A�R������ɋ}�����A�G�h�͍Ăі{���V�ƍċ��ɗ����オ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�̂ł����B
�\���� �G���@�@�@ �]�˖����A�{���V�Ƃɓ��債�A����G�a�A�Z��q�G��Ƃ�������ȏ�Ȃ����ŏG��̍˔\�͊J�Ԃ��܂����B
�G�a�̉~�n���ɔ��������đł����̂͏G�Ⴝ����l�i�G��͐�ݐ�̎荇�ƂȂ��Ă����������Ƃ͂Ȃ������j�ł���A�ӔN�̏G�a���u�����A�G�����i�炦���Ƃ��Ă��A���̏G��ɂ͂��Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�ƔF�߂Ă����Ƃ����܂��B
�G��̋}���ŁA�V����p���̂͏G�Ⴕ�����Ȃ��Ǝ������ɔF�߂��邾���̎��͂��������Ȃ���A��a�̌�ȂŏG��̋`��ł����鐨�q���G��������Ă������߂ɁA�ՖڂƂȂ邱�Ƃ𗹉�����܂���ł����B
�G�a�͂��߂ďG��̕s����a�炰�悤�悤�ƁA�G�x��Ֆڂɗ��Ă�̂ƑO�サ�ďG������i�ɏ��i�����܂��B���i�ƂȂ�Β䔯���Č���o�d�ɔ����邱�ƂɂȂ�܂����A����͏G��̑��������Ō�ɁA���ɍĊJ����邱�Ƃ͂���܂���ł����B���ӂ̏G��́A�����ېV�Ȍ�܂ʼn��x�����Q�̗��ɂł܂��B
����11�N�A�G�a�̐Ղ��p�����G�x�����_�̕a�őމB������Ȃ��Ȃ����Ƃ��A�G�x�̌Z��ł���G�h�A�S�O�Y�i�G���j�̊Ԃł́A���߂ďG��ɖ{���V���p���ł��炤�Ƃ����b�������オ��܂����B���̂Ƃ��G��ɘb�������Ă����g�҂ƂȂ�����a�̎O�j����T�O�Y�́A������{���V�Ƃ�_����S�������ďG��ɐڐG�������߁A�����m�����G�h�͕S�O�Y�𗧂ĂĖ{���V���p�����Ă��܂��܂��B
�{���V�̌�p�̘b������Ȃ���A����̂ɂ��ꂽ�`�ɂȂ�A�G��͎��]�ƕs�M������{���V�Ƃ��o�Ă��܂��܂��B
�G��͓����̑��l�҂Ƃ��Ă�������������l�����L�x�������̂ŁA�㉇�҂Ĉ͌錤����̑g�D�Ƃ��ĕ��~�Ђ�ݗ����A���̗͂��ӂ邤��܂��B�����A���荇���s���A���̊������G��̉���t���ŁA�@�֎��u���~�V��v�ɔ��\����ȂǁA��ʑ�O�ɍL��������܂����B
���E���l�҂ł���G��𒆐S�Ƃ���������ɁA���@�l�Ƃ����Q�W���ĎQ�����܂��B
�������A���~�Ђ̒��荇���@�֎��u�͌�V��v�ɔ��\����Ƃ��ɂȂ��ċ����̐Ȏ�������Ȃ����Ƃɉƌ�������F�������܂��B����͍]�ˎ��ォ��̊��K�ɏ]���A�{���V�Ɠ�����ŏ�ȁA���Ɋe�ƌ����P�ʂ̑������A�e�ƌ��̐ՖڂƂ���悤�v����ۂ܂��܂��B�܂��A�i�ʂ͉ƌ��݂̂����s���������A���~�Ђ������Ăɒi�ʂ����肷�邱�Ƃ������܂���ł����B
�G��ɂ��Ă݂�A�]�˖��{�̌�돂���������i���ɂ͉��̂�����������܂���ł������A���~�Ђ̌o�c�͎����̎�ɂ������̂ŁA��������Ƃ���ɏ]���A����̒����A���~�V��ɂ͒i�ʂ��f�ڂ��Ȃ����ƂƂ��܂����B
�Ƃ��낪�A�i�ʂɂ��Ă͎荇�̓s�����肪���������߁A�u�i�����߂Ȃ�A�Ǝ��ɋ��ʐ��Ƃ��悤�B�C�O���y������ɂ��A�i���o�[�����Ƃ����悤�ɂP����ʂƂ���ق����킩��₷���v�Ɨǂ��A�]���̏��i���X���A���l�i��i�j���P���Ƃ���A���ʐ��x��ł����Ă܂����B
�o�c�̎��������G��̎��R�ȐU�镑���ɁA�G�h�𒆐S�Ƃ����ƌ����͂��ɕ��~�Ђ��痣�E���邱�Ƃ����߂܂��B
�������A���~�Ђɂ͊��ɏG��̉��Ŋw�т����Ƃ����r�p���W�܂��Ă��܂����B�����E�̗L�͂Ȍ㉇�҂����āA�ƌ����̗��E�͉��̖��ɂ��Ȃ�܂���ł����B
�������A�{���V�Ƃ̖���ɂ��ނ��̂���A�ߋ��̌��тƂ��̉�����Ɍ��݂̌�E�����邱�Ƃ������A�ƌ����Ƃ̘a�������ӂ��܂��B
�T�N�Ԃ�ɕ��~�Ђ̒���E�ɏo�Ȃ����G�h�ɁA�u���炭�Ԃ�ł��邵�A���l�ғ��m�Ƃ��āA10�ԂقǑ����đł��Ȃ����B�v�Ǝ��������A���Ɍ����u�G��G�h�̘a���̏\�Ԍ�v���ł���邱�ƂɂȂ�܂��B
�������A���̏\�Ԍ�̓r���A�G�h�͏G��ɒ��ŏ����z�����Ƃ��ł����A���낢��ƔY���ʁA���͂̊��߂������āA�{���V�Ƃ𑶑������邽�߂ɂ͌�E�̑��l�҂��[�Ă�ׂ��ł���Ƃ��āA�G��ɖ{���V���p���ł��炤���Ƃ����ӂ��܂��B
�G��́A���ł��̘b���A�G�h�̒��������u���~�Ђ̋��ʐ���i�ʐ��ɖ߂����Ɓv�u���~�Ђ̔��s����Ə�͖{���V�̘A���Ƃ��邱�Ɓv�u�Ȍ�A�{���V�̌p���҂́A�����⎄����Ȃ����A���͑��ʂ̂��̂Ƃ��邱�Ɓv���������܂��B
�����ЂƂA������̏����Ƃ��āu�{���V�����~�Ђ̎В������C����v���Ƃ��������āA�G��͐���ď\�����{���V�ƂȂ�܂��B
�{���V�P�ʂɐ旧���A�G�h�͏\�����{���V�Ƃ��āA�G��̔��i�𐳎��ɔF�߂܂��B
�\�����{���V�ƂȂ����G��A�G�h���ܒi����Z�i�����Ď��i�ɏ��i�����܂��B
�������āA�{���V�̗��ꂪ����ւ���āA�\�Ԍ�̍ŏI�ǂ��ł���܂����B
�������A�G�Ⴊ�{���V�ɏA���Ă���3������A����ȏP�ʎ��̏����܂ł��Ă��Ȃ���G�Ⴊ�}�����܂��B�G�Ⴊ�{���V�Ƃ��đǂ����̂͌��ǏG�h�Ƃ̏\�Ԍ�ŏI�ǂ݂̂ł���A���ꂪ�G��̐�ǂƂȂ�܂����B
���̋}�W�J�ɁA�G�h�͍����̂Ȃ��Ăі{���V�Ƃ��x���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B
�\�㐢 �G�h�i�ďP�j �@�@�G��̎��ɂ���āA�ēx�{���V�ƂȂ��������̏G�h�́A�ďP�ł͂Ȃ��A�\�����{���V�Ƃ��Ď��Ԃ����E���Č�p�҂��߂�S�ς��肪����܂����B
��E�̑��l�҂��{���V�A�܂����~�ЎВ��ƂȂ邱�Ƃ��G��Ɩ������Ƃ���A�G�h�͕��~�Ђ̎��Ȃł��钆��T�O�Y�Ə������ł��Ƃ���]���܂����B
�������A����ƕ��~�Б��́A�������ł����ɒ���T�O�Y�ɑS�đ���������ׂ��Ƃ����A�G�h�ƏG��̘a���̘J��������㓡�ێ��Y�����~�Ђ̑��ɂ��ďG�h�̐����ɉ��܂����B
�G�h�͂����܂ł������ɂ���Č��߂邱�Ƃɂ������A����͏������̔�������������ĕ��~�ЎВ��̒n�ʂ����͎�낤�Ƃ��āA�����͖{���V�Ƃ��p�����肪�Ȃ��Ə��������ނ��A�����ɕ��~�Ђ�2��ڎВ��ɏA���Ă��܂��܂��B
����ɂ���āA�G��Ɩ����{���V�ƕ��~�Ђ̊W�͉i�v�Ɏ����邱�ƂɂȂ�܂����B�����Đ����ɏG�h���{���V���ďP�A�\�㐢�ƂȂ�܂����B
�G�h�͏G��Ƃ̏\�Ԍ���o�č˔\���J�Ԃ��A���u�Ɓu�͌鏧���v���B���̑g�D�W�����Č���荇�ƌ�i�̎w����ړI�Ƃ����u�l�ۉ�v�𗧂��グ�܂��B
���łɂ��̂���͑��l�҂ƂȂ����G�h�̉��ɂ͑����̒�q���W�܂��Ă��܂����B���̒��ɂ͂����Ă͕��~�Ђ̏m���ł��������̑����A���21���G�ƂƂȂ�c���ێ������܂����B
�G�h�́A����38�N�Ɏ��͂̌㉇�̑E�߂ɂ�薼�l�ɐ�������܂��B�]�˖��{�̌鏊�ƊW�̂Ȃ����߂Ă̖��l���a�����A�u���{�͊���v��ݗ����Č�E�̓����ڎw���܂��B
�������A�G�h���G��̎��Ɠ����悤�Ɂu���ꂩ��v�Ƃ����Ƃ��ɂȂ��Đ��������Ă��܂��܂��B���l�A�ʂ���7������̂��Ƃł����B
�ӔN�͌�p�ґI�тɋꗶ���A�|�̏�ł͓c���ێ��i��̏G�Ɓj�������ɍł��߂��ƔF�߂Ȃ�����A�l�i�ʂő��e��Ȃ����̂�����A��Ԃɖڂ��|���Ă���������ꂪ�A�Ȃ�Ƃ��c����ǂ������Ă���Ȃ����Ɗ��҂��Ă��܂����B��p�҂��w�����Ȃ��܂ܖS���Ȃ������ƂŁA�܂��p���Җ�肪�������邱�ƂɂȂ�܂��B
��\�� �G���i�ďP�j �@�@�G�h���S���Ȃ�ƁA�{���V���́A�G�h������p���������Ǝv���Ă�����������i������u�G�h���S�l�܂��q�h�v�ƁA����ɔ��������͑��ʂ́u�c���ێ��h�v�ɕ��鎖�ԂƂȂ�܂����B
���E�����Ȃ��Ȃ����������E���邽�߂ɁA�c���Ɂu�B���G������������Ղ��p���A�{���V����̎��i�������ēc���ɏ���悢�v�ƒ�Ă��A�[�������܂��B
���̂Ƃ��A����͒i�ʂ̏�ŘZ�i�A�c���ɂ͋y�Ȃ����߂ɁA�����ɖ{���V���p�����邱�Ǝ��̂ɖ��������������߁A�G�������ĂA�G�h�̒�ł����邵��������_���邱�Ƃ��ł��܂���B
�G�����g�́A���l�҂łȂ����̂��{���V�Ƃ̓���ɂ����Ƃ̕s�s����g�������Ēm���Ă��܂����B
�������āA���Ԃ𗎂�����������A�G���͉��߂Ď����̈ӎv�Ƃ��āA���͂̒ʂ�c�������̖{���V�Ɏw�����܂����B
��\�ꐢ �G�� �@�@�@�G�Ƃ́A�G�h����������m����ȉ��̑ł����Ȃ��A�B������ێ����A�{���V�ƂȂ��Ă���͏�����ɂ��Ƃ��Ƃ����������߁A�s�s�̖��l�Ƃ����Ȃ���A���̖��l�ɔ�ׂĕ]�������܂ЂƂȂ̂́A���Ă̏G�h�����l�D�݂̎���������������|���ł���̂ɑ��āA�͐�h�œD�L����ۂ�����A�Ǎ��̊��m�Ƃ��Đl�����肪���������ʂ����邽�߂�������܂���B
�c���ێ��i�G�Ɓj�́A���߂͏G��̕��~�Ђ̏m���ƂȂ�܂����B�������A���~�Ђł͂���������т��Ȃ��A�Ə����s����܂���ł����B
�G�Ⴊ�S���Ȃ�A2��ڎВ�����T�O�Y�̎���ɂȂ��Ă��A�c���͓��i�������ꂸ�A���~�ЂƉƌ����̒i�ʁi���~�Ђ͋��ʁj�̐H���Ⴂ�Ȃǂ����Ă����c���́A���m�Ƃ��Ă̐����Ɍ�����������ĕ��~�Ђ��o�Ă��܂��܂��B
�Ƃ͂����A�q���̂��납��͌��{�̐��������Ă����c�����A���܂���ʂ̐��������ł���킯���Ȃ��A���Ƃ����Ĕ�яo�������~�Ђɖ߂邱�Ƃ��ł��܂���ł����B���͂ň͌�w��̌m�Ï���J�������̂́A19�Ζ��i�̏��N���m�ɏK���ɂ��邱�Ƃ��Ȃ��A���~�Ў���Ɋ猩�m��ƂȂ������ʋςɗ���ŏG�h�Ɉ������킹�Ă��炢�܂����B
�G�h�͓c���ƂR�q�łR�ԑł��A3�A���B�荇�����Q�q�Ԃ����������߂܂����B�G�h�͓c���Ɂu���i���~�������v�ƕ�����āA�c���͌ܒi���~�����ƌ��������ĕs���Ǝv���Ă͂����Ȃ��ƁA�l�i���肢�A�����ɋ�����܂��B
�G�h�̔ӔN�A���͂̑S�Ă��q������܂őł����Ȃ��A�c���ЂƂ��ŝh�R���Ă��܂����B�������A�G�h�̑��̒�q�ɔ�ׂēc���͏G�h�Ƃ̑ǂ����Ȃ��̂́A���͓I�ɂ�����l������ǂ����̂����ɁA����ƋC�y�ɑłĂ�悤�ȑ���ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ������ƂƎv���܂��B
�c���͏G�h�Ƃ̑ǂ͂Ȃ��Ƃ��A���̊��m���G�h�Ɠ����悤�ɑł�����ł��܂����̂ŁA�G�h�����i�ƂȂ�Ƃ��ɓc����Z�i�ɐi�߁A����Ɏ��i�ɂ����߂āu�c�����i�̐���ێ��ł��鎩���͋�i���Ȃ킿���l�ł���v�Ɩ����̎咣������z��~�����ƌ����܂��B
�ŏ��́A�G�h�ɖڂ��������Ă����c���́A���̐��i�I�Ȗʂ��玟��ɑa����悤�ɂȂ�܂��B
�c���͌Ȃ̗��Q�ɐ����ɏ]���A�����̗݂͂̂�M���A�G�h�̐������Ɛ����ł����̂ŁA���ۂɂ��̊��͂��G�h�ɋ߂Â����Ƃ��ɁA�Ƃ����茩����悤�ɂȂ���遖��ȑԓx���G�h�ɂ͎�����܂���ł����B�G�h�̖ڂ͏������Ɋ��҂��Ă����������Ɍ�������悤�ɂȂ��Ă����܂��B
����͎��͂œc���ɋy�Ȃ����̂́A���V�ȑԓx�Ɨ�V���������C�ɓ����܂����B�܂��A�c���̍s���͉����ƏG�h�ƏՓ˂��܂��B���ɁA�c��������Ƃ̗{���ړ��Ăɕp�ɂɈ���Z�p�̎���ɏo���肷�邱�ƂŁA�c���͖{���V�Ƃ̐Ռp���Ƃ��ē��Ăɂ͂ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƍl����悤�ɂ��Ȃ�܂����B
�G�h�͖��l�ƂȂ����N�̏H���猋�j�ɂ�����A�Ֆڂ̖�肪�����������тĂ��܂����B������Ȃ�ǂ��������ɖK���̂ɑ��āA�c���͌����������ۂ���A�G�h���ĂɎ莆�ŕs�����Ԃ��܂��B
�u���͏��Ȃ玩�����Ֆڂɒ�߂��Ȃ��̂͂Ȃ����B�������������āA���~�Ђ���]���ĂQ�N�Ă��ǂ̊��
�ɈƑւ�������肩�v
�G�h���g���A����̍˔\��M���Ă�����̂́A����̎��͂ł͂܂��c���ɋy�Ȃ����Ƃ͂킩���Ă��܂����B���̒��O�A�����Z�i�ɂ܂Ői�߂܂����A�Ֆڂ̎w���܂ł��S�O�������̂��A�܂��Ȃ��G�h�͐�������܂��B
�����ŐՌp���ɂ��āA�G�h�̈ӌ��ł���Ƃ������h�ƁA���͏��łȂ�ׂ��Ƃ����c���h�ɕ�����A�O�q�̓�\���{���V�G�����o�āA��\�ꐢ�G�Ƃ��a�����܂��B
�G�Ƃ͔��i�����l�ɏ��A�吳���̌�E�œG������̂͂��łɂ���܂���ł����B�������A�G�Ƃ̍ŏI�ڕW�́A���l�ƂƂ��Ɍ�E�̓���ɂ���܂����B
�G�Ƃɒ���ۂ��Ă������̂́A�L�������Y�A����A���_���g��3���B�L���͌��N��̗��R�Ŏ荇������A����͑ǂ��������܂���B���_��l��������ē��邯��ǁA�|�őΓ��ɗ�������������̂����Ȃ��ȏ�́A�G�Ƃ̖��l�͂�����W���邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B
�G�Ƃ����l�ƂȂ��������A�сA����Ƃ͂��łɒf�₵�A���Ƃ͊��ɈڏZ���Ă��낤���đ������Ă��܂����B���Ƃł͏\�ܐ����ׂ̖v��̐ՖڂɁA�{���V���p�����荇���牓�������Ă�������𗧂Ă悤�Ƃ��܂����A�����̌b���c�h�F�������\�Z����]��ł��邱�Ƃ�m��ƁA�Ֆڑ�������~��Ă��܂��܂��B
�������A����1���������͎荇�ɖ߂�C�������킢�Ă��܂����B
�L�������Y��5��ڎВ��߂���~�Ђɕ��A���A�P�U�N�Ԃ�ɏG�Ƃ�3�ǂ̎荇���g�܂�A�P���P�s�P�ł��|���ƂȂ�܂����B
�G�Ƃɂ��Ă݂�ƁA�������܂ߏC�s����̃��C�o���������A���łɂ���������߂������̂̎荇�����A���ꂩ��̃X�^�[���A��؈��Y�A���z����炪�ォ�甗���Ă���̂����킷�̂ɋ�J�A�G�ƂƂ��ẮA�K�R�ނ�Ƃ̑ǂ������悤�ɂȂ�܂����B
��A���z�ɑ����āA���~�Ђ̍L�����Q�����A�ނ炪���S�ƂȂ��Č𗬎荇�͈�ʓI�ɂȂ��Ă��܂����B
���̔ނ�́A�ߋ��̂������ɂ�������ĕ��I�ɂȂ��Ă����Ԃ�J�����A��E������n�����������ƍl���Ă��܂����B
�h�����āA�{���V�ƁA���~�Ђ̎�荇���ɂ�錤����u�Z�؉�v�������B�ŏ��U�l����n�܂�܂������A�Ō�ɓ��{���@�ɎQ�W���邳���ɂ͂Q�Q������Ȃ錤����ɂȂ��Ă��܂����B
�吳�P�O�N�ɂ́A�G�Ɩ��l�𒆐S�ɋ�̓I�Ȍ�E�ē���^���Ƃ��āu���{�͌鋦��v�Ă������オ��܂����B�������A�G�Ƃ͕ʊi�Ƃ��āA���̑��̂��͎̂荇�̐��тɊւ�炸���i�͓��i�Ƃ����s���ɕ����Ȉ������������Ă����̂ŁA�ꕔ�̊��m���Ǝ��̌�����ł���u�鐹��v���g�D����܂��B�ŏ��̉���́A����A��؈��Y�A���������A���z����̂S���ł����B
�鐹��́A���ݐ搧�A���ԑŊ|�����̔p�~�A�_�����̗̍p�ȂǁA�v�V�I�ȉ�Ƃ��A�G�ƂɁu�������ɏ�������v�Ɣ������̂ł����B
�鐹��ɐݗ��́A���{�͌鋦��̔����ɐ��������܂������A�����āA�鐹��ɂ���ėL�͉�������������~�ЂƏG�Ƃ��������āA�u�������@�v��ݗ����܂��B�������A�킸���R�����Œ��Ԋ���A���~�Б��̒E�ނɂ���āA��E�͖{���V�ƁA���~�ЁA�鐹��̎O�h�ɕ��܂����B
�����ɑ吳12�N�֓���k�Ђ��N����A�e�h�͑S�Ă̊�Վ����Ă��܂��܂��B������@�ɁA���ł��Ƃ����m��ʊ��m���������邽�߂͑傫�Ȉ�̑g�D�ɏW�����邵���Ȃ��ƁA������q�쎵�Y�j�݂ɉ����𗊂݁A���{���@���n�����܂��B
�������A�n���̒���A�K��ᔽ�ɂ�����A��A�����̌��鐹��A����ɉ����M�A����c��㑾�Y����������܂��B���R�́A���{���@�̊����͊e�V���҂ƌ_�Ē��I�Ŕz�����邱�Ƃɂ����̂ɁA��������������s���Ɏv���Ă�����m�V���ЂƁA�ϋɓI�Ɋ����f�ڂ�]�ފ��m�����������̂ł����B
�ނ�́A��m�V���̌㉇�āu�����Ёv�𗧂��グ�܂��B
�̂��ɁA�����A����c�����A���A�R�l�ƂȂ��������Ђ́A�ǔ��V���В����͏����Y����āA�����ЂƓ��{���@�̑R���Â����������܂��B���͂́A�V���̍w�Ǖ�����L�����߂Ɉꔭ���Ă悤�Ǝv���Ă����Ƃ���A���̊��ɔ�т��A���@�Ɗ����Ђ̑R������������܂��B
�@�БR��Ƃ��Ė��������̏���́A�����Ȃ�̑叫����B�G�ƂƊ������n�߂��܂��B
�G�Ƃ̐Ύ���Ƃ��Ē����ȂP�ǂ́A�����m�̌�ł͂߂����Ɍ����Ȃ���U�ߍ����ƂȂ�܂����B���ԂŏG�Ƃ͈��S�ő��̒���������I���A�ґR�Ɗ���̍������ɍs���A�݂��ɂQ�O�ڈȏ�̑���U�ߍ����ƂȂ�A���̊��������邽�߂Ɍf�ڐV���͔��s������L���A�ǂ��炪�������Љ�I�ȊS���ɂ܂łȂ�܂����B
���ʂ́A�U�ߍ����𐧂����G�Ƃ�����̎��Ԑ�ŏ����i�Ֆʂł��D���������j���A�Q��ڈȍ~�́A�G�Ƃ͑ނ��Ċ��@�̐��s��\�Ɗ����Ђ̏��������킪�s���A�������i����̎荇�ł��������߂ɁA�����炩�Ɋ��@���̎��ɕ��������āA���ʂ͊����Ђ̎S�s�B�r���A����c�����@�ɕ��A���āA�����Ђ́A������ƍ��������ɂȂ��Ă��܂��܂����B
�����Ђ�ނ��āA���{���@�͈͌�̑��{�R�Ƃ��Ă̊�Ղ����X�Ɉ��肵�Ă��܂����B
���a2�N�A�]���̒莮�荇��p���A�����V�����X�|���T�[�Ƃ����荇���n�܂�܂��B���m�̐��т�A�N�����i���邩�ȂǁA��ʂ̈͌�t�@���ɍL���ڂɐG���悤�ɂȂ�A�ؒJ�A�������̐V�z��A�ǔ��̑I�茠��ŗD�������������ƁA�G�Ƃ̋L�O��i����1��ڎO�X�A3��ڐ��A5��ړV���ɑł������ƂŗL���j�Ȃǂ����������ɁA�e�V���Ђ͈͌闓�ɃX�y�[�X�������悤�ɂȂ�܂����B
���������V���́A��Ə����̗����ɂ��Ė��l�����悵�܂������A�����̏\�O�����l�֍������Y�͂����Ɏ���̗���������Ĕ[�����܂������A�͌�E�͒i�ʂƎ荇���̊i�����������A���ݐ�̑I�茠�ɂ͍ŏ��[�����܂���ł����B
�����ŁA�̈ӂɒi����ɂ��I�茠����Q�x�J�Â��āA�l�i�ƘZ�i�̗D���҂��o��Ƃ������������邱�Ƃɂ���āA�u���͑��ʂ����߂�̂ɁA�i����ł͏�̂��̂������v�Ƃ������Ƃ�[�������܂����B
�������A�Ȃ����D���҂̏̍��ɂ��ďG�Ƃ́u���l�v�ł͂Ȃ��u�{���V�v�̖��Ղɂ������܂����B���{���@�̑n���Ԃ��Ȃ�����A�G�Ƃ͐ՖڂɂƊ��҂��Ă������ݑs���a�C�Ŏ����Ă��܂����B���ݖS����A�{���V�̐ՖڂɔY��ł����Ƃ���ɖ��l��̘b������A����A�{���V�̖��Ղ�I�茠�ŏ����������ō����͎҂Ɍp���������B���{���@�̎Ⴂ���m�݂͂�Ȏ����̒�q�̂悤�Ȃ��̂��A�ƍl���܂����B
�������āA�{���V�̖��Ղ�V���Ђ������A���{���@�Ɋ�����D����I�茠����J�Â��邱�ƂɂȂ�u�{���V���Ց��D�S���{�����m�I�茠��荇�v�Ɩ��Â����܂��B
�I�茠��ɐ旧���Đ��P���Ō�̖{���V�A�G�Ƃ̈��ގ��Ƃ��ċL�O�邪�s���܂��B
���ތ�̑ǎ҂͑I����������������ؒJ�����i�B�������Ԋe40���ԁA���߂ĕ����萧�x���p�����܂����B
�ł��p��15��A�r���G�Ƃ̕a�C���@�ɂ��3�����̒��f�������āA6�����ɂ킽�钷���ǂ́A����̏G�Ƃ̗͓͑I�ɖ���������܂����B
�G�Ƃ͖ؒJ���i�̐���������ɂ܂킵�Ē��Ղ܂ł͌`���s���ł������A�a�C���f�̉e���������āA����ɏ\���ȑ̒��ł͑łĂȂ��Ȃ�܂��B����Ȓ��ŖؒJ�̕�������u���ԃc�i�M�̖��ߎ��ł��āA�x�݂̊ԂɌ������悤�Ƃ����v�ƌ��ߕt���A��Â����������P��̎����ɂ���Č`���˂Ă��܂��܂��B��ɁA���̌�̉���������Ƃ��ɂ́A�G�Ƃ͂��̎���u�����ł����ł���v�ƔF�߂��悤�ɁA�̒����܂܂Ȃ�Ȃ��G�Ƃ��Z�C���N�����Ă��܂����̂ł����B
���a13�N6���ɊJ�n���ꂽ���ތ�́A���N12���A�ؒJ���i�̂T�ڏ����ɏI���܂��B�ؒJ�̏���Ԃ�34���ԁB�G�Ƃ���20���Ԃ��g���A�Ō�̏�����Ő����s���ʂĂĂ��܂��A���̖�1�N��A�V�����I�茠��ɂ��{���V�̒a�������邱�ƂȂ��A��������܂����B